こんにちは、Dayです!
このブログでは、最新の脳科学論文を一般の方にも楽しめるようにわかりやすくまとめています。
今回のテーマは「思春期の社会不安と親の育て方の関係」についてです。
思春期になると「人前で緊張しすぎる」「友達と話すのが不安」といった社会不安を抱える子どもが少なくありません。では、その背景にはどのような要因があるのでしょうか?
最新の研究では、母親と父親それぞれの関わり方が子どもの不安に異なる影響を与えることが示されました。特に、親の「温かさ」や「過干渉(統制)」といった養育スタイルが、子どもの社会不安の強さに関係しているのです。
本記事では、複数の研究を統合したメタ分析の結果をもとに、母親と父親の養育行動が子どもの社会不安にどのように影響するのかをわかりやすく解説していきます。
本記事は、以下の研究をもとにしました。
Howard, C. J., Oshri, A., Card, N., Muñoz, M., Thomas, C. R., & Brown, G. L. (2025). Perceived mother and father parenting and adolescent social anxiety symptoms: A meta-analysis. Adolescent Research Review. Advance online publication.
https://doi.org/10.1007/s40894-025-00268-0
思春期の「社会不安」とは?
思春期は、心と体が大きく変化し、人間関係の幅も一気に広がる時期です。友達や先生、異性との関わりが増える一方で、「どう思われているのだろう」「恥をかいたらどうしよう」といった不安を感じやすくなります。
このような人前での強い緊張や不安は「社会不安」と呼ばれ、次のような場面でよく表れます。
- 授業中に発表するときに声が震える
- 初対面の人と話すのが怖い
- グループ活動でうまくなじめず孤立してしまう
- 友達にどう思われるか気になりすぎて疲れてしまう
一時的な緊張なら誰にでもありますが、これが強すぎたり長引いたりすると、学校生活や友人関係に大きな影響を与えてしまいます。例えば、授業に参加できなくなる、友達づきあいを避ける、といった行動につながることもあります。
思春期の社会不安は珍しいことではなく、多くの子どもが少なからず経験するものです。だからこそ、「親の関わり方」がこの不安を和らげるのか、それとも強めてしまうのかを科学的に調べることは、とても重要なのです。
親の育て方と子どもの不安の関係
親の関わり方は、子どもの心の発達に大きな影響を与えます。特に思春期は親の存在がまだ大きく、接し方によって子どもの「安心感」や「不安感」が強まることがわかっています。
研究では、親の育て方を大きく2つの側面に分けて考えています。
「温かさ」が不安を和らげる科学的根拠
「温かさ」とは、子どもに対して愛情を示したり、サポートをしたりする姿勢のことです。
- 子どもの話をしっかり聞く
- 励ましたり安心させたりする
- ありのままを受け入れる
こうした関わりは、子どもに「自分は大切にされている」という感覚を与え、結果的に社会不安を軽減することが示されています。
心理学的に言えば、温かさは「安心の基地」となり、子どもが外の世界に挑戦する勇気を支えてくれるのです。
「統制(過干渉)」が不安を強める仕組み
一方で「統制」とは、親が子どもの行動を強くコントロールしたり、過度に口を出したりする関わり方を指します。
- 失敗を許さず、細かく指示を出す
- 子どもの意見よりも親の考えを優先する
- 常に「こうしなさい」と管理する
このような過干渉は、子どもに「自分には決める力がない」という感覚を植えつけ、自信の低下や不安の強まりにつながります。社会的な場面で「どうすればいいのかわからない」という不安を感じやすくなるのです。
つまり、親の「温かさ」は不安を和らげ、「統制」は不安を強める。
これが研究から見えてきたシンプルだけれど大切な関係性です。
母親と父親、それぞれの影響の違い
親の育て方が子どもの社会不安に影響することはわかっていますが、母親と父親では、その効果に違いがあるのでしょうか? 最新のメタ分析研究では、この点を詳しく調べています。
母親の影響
- 温かさ:母親が子どもに温かく接することは、不安を軽減する方向に働くことが示されました。日常的な声かけや共感的な態度が、安心感を支える大きな要素になります。
- 統制(過干渉):一方で、母親による過度な統制は、子どもの社会不安を高める傾向が確認されました。細かすぎる指示や心配しすぎる対応は、子どもに「自分でやれる力がない」と感じさせ、不安を強めてしまいます。
父親の影響
- 温かさ:父親の温かさも、不安をやわらげる効果があるとされています。父親との関わりは特に「挑戦を促す」「新しい経験を一緒にする」といった形で現れやすく、子どもの自信につながる可能性があります。
- 統制(過干渉):興味深いことに、父親の統制については有意な影響が見られませんでした。母親ほど子どもに密接に関わらない場面が多いためか、父親の「口出し」は子どもの不安に直結しにくいのかもしれません。
違いのまとめ
この結果からわかるのは、母親と父親は同じ「親」でも影響の仕方が異なるということです。母親の温かさと過干渉は、子どもの不安に強く関わる一方で、父親は「温かさ」がプラスに働きやすいが「統制」は目立った影響を与えにくい。
つまり、両者はそれぞれ違った形で子どもの心に影響を与えているのです。
メタ分析で見えた一貫した傾向
今回の研究が特徴的なのは、単一の調査ではなく「メタ分析」という手法を用いている点です。
複数の研究を統合する「メタ分析」とは?
メタ分析とは、過去に行われた複数の研究データを統合し、全体としてどのような傾向があるのかを統計的に検証する方法です。個々の研究ではサンプル数が少なかったり、結果にばらつきが出たりすることがありますが、メタ分析ではそれらをまとめることで、より信頼性の高い結論を導き出せます。
今回の研究では、さらに「構造方程式モデリング」という分析手法を組み合わせることで、母親と父親の影響を同時に扱い、それぞれの「独自の影響」と「共通の影響」を区別して明らかにしました。
信頼性の高いエビデンスとしての意義
その結果、以下のような一貫した傾向が確認されました。
- 母親・父親ともに「温かさ」は子どもの不安を軽減する効果がある
- 母親の統制は不安を強める方向に働く
- 父親の統制には有意な影響が見られない
このように、複数の研究をまたいでも同じ結果が得られたことは、「偶然の発見」ではなく、社会不安と親の育て方の間に安定した関係が存在することを意味します。
親としてできること ― 子どもの不安を和らげる関わり方
研究の結果は、親の「温かさ」が子どもの安心につながり、「過干渉」が不安を強めることを示していました。では、日常生活の中で親はどのように関われば良いのでしょうか?
愛情表現とサポートの重要性
- 子どもの話を「うん、そうなんだね」と受け止める
- 失敗しても「挑戦したこと自体がすごい」と声をかける
- 不安な気持ちを否定せず、「大丈夫、一緒に考えよう」と寄り添う
こうした小さな積み重ねが、子どもにとって「自分は大切にされている」という確信につながり、安心して人間関係に向き合う力を育てます。
過干渉を避けるための工夫
- 子どもがやりたいことに挑戦させてみる
- 失敗をすぐに止めず、「どうすればいいかな?」と考えさせる
- 子どもの選択を尊重し、親の価値観を押しつけすぎない
親にとっては心配でも、子どもにとっては「自分で決めた」という体験が大きな自信になります。過干渉を減らすことは、不安を防ぐだけでなく、将来の自立心を育てることにもつながります。
母親と父親の両方が大切
研究では、母親と父親の影響が少しずつ違うことも明らかになりました。だからこそ、母親の安心感と、父親の挑戦を支える温かさの両方がそろうことが、子どもの成長にとって理想的だといえます。
まとめ|母親と父親、両方の関わりが子どもの安心につながる
思春期の社会不安は、多くの子どもが直面する自然な心理的課題です。その背景には「親の育て方」が関係していることが、最新のメタ分析研究で明らかになりました。
- 母親と父親の「温かさ」は、不安をやわらげる大切な要素。
- 母親の「過干渉(統制)」は、不安を強めるリスクになる。
- 父親の統制は大きな影響を示さないが、温かさは子どもの安心を支える。
つまり、子どもの不安を減らすためには、親が「温かく寄り添い、サポートする姿勢」を持つことが最も大切だといえます。
母親と父親がそれぞれの強みを活かして関わることで、子どもは安心感を抱き、人間関係や社会生活に前向きに挑戦できるようになるのです。
親の接し方は、子どもの未来に大きな影響を与えます。日常の小さなやりとりの中で「温かさ」を意識することが、思春期の不安をやわらげる一歩になるでしょう。


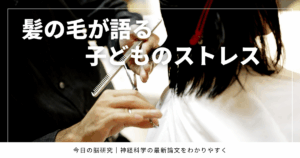
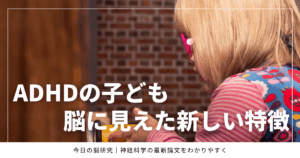
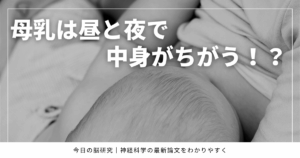
コメント