こんにちは、Dayです!
このブログでは、最新の脳科学論文を一般の方にも楽しめるようにわかりやすくまとめています。
今回のテーマは「髪の毛から子どものストレスがわかる?慢性疾患と心の健康をつなぐ最新研究」についてです。
慢性疾患を抱える子どもたちは、病気の治療や通院に加えて、学校生活や日常生活でもさまざまなストレスにさらされています。その結果、不安や抑うつ、行動の問題といった「心の不調」が起こりやすいことが知られています。
では、その“目に見えないストレス”を、どうやって把握できるのでしょうか。
最近の研究では、髪の毛に蓄積される「コルチゾール」というホルモンを調べることで、子どもの長期的なストレス状態を測れることが分かってきました。まるで髪の毛が、心の状態を記録している“ストレスのタイムカプセル”のように働くのです。
今回紹介する最新の研究では、慢性疾患をもつ子どもの髪の毛からストレスホルモンを測定し、その変化のパターンと心の健康との関係を明らかにしました。「ストレスは高いか低いか」だけでなく、「時間とともにどう変化するか」が、子どもの心の不調と深く結びついていたのです。
この記事では、この研究の内容をわかりやすく解説しながら、「髪の毛でストレスを測る」科学の面白さや、子どもの心の健康を守るための新しい視点について紹介します。
本記事は、以下の研究をもとにしました。
Littler, E. A. L., Butt, Z. A., Gonzalez, A., & Ferro, M. A. (2025). Association between hair cortisol and psychopathology in children with a chronic physical illness. Stress and Health, 41(4), e70087.
https://doi.org/10.1002/smi.70087
髪の毛でストレスがわかるって本当?
「ストレスがたまっているかどうか」を知るには、ふつうはアンケートや本人の自覚に頼ることが多いですよね。しかし、科学の世界では“客観的なサイン”を探す研究が進んでいます。その一つが 髪の毛に含まれるコルチゾール です。
コルチゾールは、体がストレスを感じたときに分泌されるホルモンで、一般に「ストレスホルモン」と呼ばれています。これまでは血液や唾液で測定するのが主流でしたが、これだと一時的なストレス反応しかわかりません。
一方、髪の毛は1か月に約1センチ伸びるため、毛髪に含まれるコルチゾールを調べれば、過去数か月間のストレスの蓄積を知ることができるのです。たとえば、根元から3センチの毛髪を分析すれば、およそ3か月間のストレス状態を“履歴”として読み取れるわけです。
つまり、髪の毛はただの外見の一部ではなく、心と体がどのくらいストレスにさらされてきたかを記録する「タイムカプセル」のような存在。最新の研究では、この髪の毛のデータをもとに、子どものストレスや心の健康状態をより正確に把握しようと試みられています。
慢性疾患をもつ子どもの心の健康問題
慢性疾患(ぜんそく、糖尿病、てんかん、心臓病など)を抱える子どもたちは、日常生活の中で多くのストレスに直面します。
定期的な通院や検査、薬の服用に加えて、体調の変動によって学校行事や友達との遊びに参加できないことも少なくありません。
こうした状況は、「病気そのものの負担」だけでなく、「心の負担」も大きくします。
実際に、慢性疾患をもつ子どもは、健康な子どもに比べて 不安や抑うつといった内面的な問題 や、イライラ・攻撃的な行動といった 外向きの問題を経験しやすいことが知られています。
さらに、慢性的な病気は「長く続く」ことが特徴のため、子ども自身だけでなく家族も含めて、心理的なサポートが欠かせません。親が心配しすぎたり、逆にサポートが十分でなかったりすると、子どものメンタルに影響する可能性もあります。
つまり、慢性疾患をもつ子どもたちの心の健康を守るには、身体の治療と同じくらい、心理的なケアも重要なのです。では、その“見えにくいストレス”をどうやってとらえればよいのでしょうか? そこで注目されているのが「髪の毛に残るコルチゾール」という新しい科学的手法です。
最新研究でわかった「髪の毛と心の関係」
カナダの研究チームは、慢性疾患をもつ子どもたち244人を対象に、髪の毛のコルチゾール量と心の健康との関係を約4年間にわたり追跡しました。対象となった子どもは2歳から16歳までで、ぜんそくや糖尿病、心臓の病気など、さまざまな慢性疾患を抱えていました。
研究では、髪の毛の3センチ部分を切り取り、そこに含まれるコルチゾール量を定期的に測定しました。髪は1か月に約1センチ伸びるため、3センチ分の毛髪はおよそ3か月間のストレス履歴を反映しています。
解析の結果、子どもたちの髪の毛コルチゾールには次の 3つのパターン があることがわかりました。
- ずっと高い状態(Hypersecretion)
- ずっと低い状態(Hyposecretion)
- 最初は高いが、だんだん低くなる状態(Hyper-to-Hypo)
そして驚くべきことに、心理的な不調(不安・抑うつ、行動問題など)がもっとも多かったのは「ずっと高い状態」の子どもたちでした。一方、「最初は高くても徐々に下がった子ども」では、心の不調が比較的少なかったのです。
つまり、ストレスホルモンが「高いか低いか」よりも、時間とともにどう変化するか(ストレスの軌跡) が、子どもの心の健康に深く関わっていることが示されたのです。
科学的におもしろいポイント
この研究には、一般の人が聞いても「なるほど!」と感じる科学的な魅力がいくつもあります。
① 髪の毛が“ストレスの履歴書”になる
髪の毛はただの外見の一部ではなく、過去数か月のストレスの蓄積を記録する「タイムカプセル」のような存在です。血液検査や唾液検査が「その瞬間のストレス」しかわからないのに対し、毛髪は長期的なストレスの推移を見られる点がユニークです。
② ストレスは「高い・低い」よりも「変化の仕方」が重要
単にコルチゾールが高いから不調になるわけではありません。今回の研究では、ずっと高いままの子どもが心の不調を抱えやすく、一方で「高いけど徐々に下がる」子どもは比較的安定していることがわかりました。これは、ストレスの科学を“静止画”ではなく“動画”で捉える必要があることを示しています。
③ 心と体をつなぐ新しい視点
慢性の病気という「体の問題」が、ストレスホルモンを通じて「心の不調」と結びついていることを、科学的に裏づけた点も注目に値します。体の病気を治すだけでなく、心のケアも重要だとあらためて示しているのです。
④ レジリエンス(回復力)が見えるかも?
最初はストレスホルモンが高くても、その後下がっていった子どもたちの方が心の不調が少なかったことから、「ストレスから回復する力(レジリエンス)」を客観的に測れる可能性が出てきました。これは将来、子どものメンタルケアを科学的にサポートする新しい方法になるかもしれません。
この研究からわかること・今後の可能性
今回の研究で明らかになったのは、子どもの心の不調は「ストレスが高いか低いか」だけでなく「その変化の仕方」に深く関わっているということです。慢性疾患をもつ子どもでは、ストレスホルモンがずっと高いままだと不安や抑うつ、行動の問題につながりやすく、逆に少しずつ下がっていく場合には心の健康が守られる可能性があることがわかりました。
この知見は、医療や教育の現場で大きなヒントになります。たとえば、髪の毛を切って調べるだけで、子どもが「どのくらいストレスを抱えているか」「回復できているか」を把握できるようになれば、心の不調を早めに察知し、サポートにつなげることができます。
さらに、学校や家庭でも応用できる未来が考えられます。定期的に毛髪コルチゾールを測ることで、子どものストレス状態を客観的に把握し、心理カウンセリングや生活習慣の見直しを効果的に行えるかもしれません。
もちろん、まだ課題もあります。髪の毛のケア(染色や洗浄)や生活環境による影響、サンプル数の制限など、研究の限界を踏まえる必要があります。しかし、それでも「髪の毛から心の健康を読み取る」という発想は、子どものメンタルケアに新しい道を開く可能性があります。
今後は、より大規模な研究や異なる国・文化での調査、そして介入研究(心理的サポートが毛髪コルチゾールをどう変えるか)が進むことで、髪の毛を使ったストレスチェックが、医療や教育の現場で一般的になるかもしれません。
まとめ|髪の毛で“心の健康”を見える化する時代へ
髪の毛に含まれるストレスホルモン「コルチゾール」を調べることで、慢性疾患をもつ子どもたちの心の健康状態を把握できる――。今回の研究は、そんな未来を感じさせる内容でした。
ポイントは、ストレスが単に「高いか低いか」ではなく、時間とともにどう変化していくかが心の不調に大きく影響するということ。これは、子どもの心を理解するうえで新しい視点を与えてくれます。
髪の毛を使ったストレス測定は、痛みもなく手軽にできる方法です。将来的には、医療の現場や学校、家庭でも、子どものストレス状態を客観的に確認できるツールとして活用されるかもしれません。
「体の病気を治す」だけでなく、「心のケアにも目を向ける」ことが、慢性疾患をもつ子どもたちの生活の質を高める大切なカギになります。髪の毛という身近なものから心の健康を見える化できる時代は、すぐそこまで来ているのかもしれません。
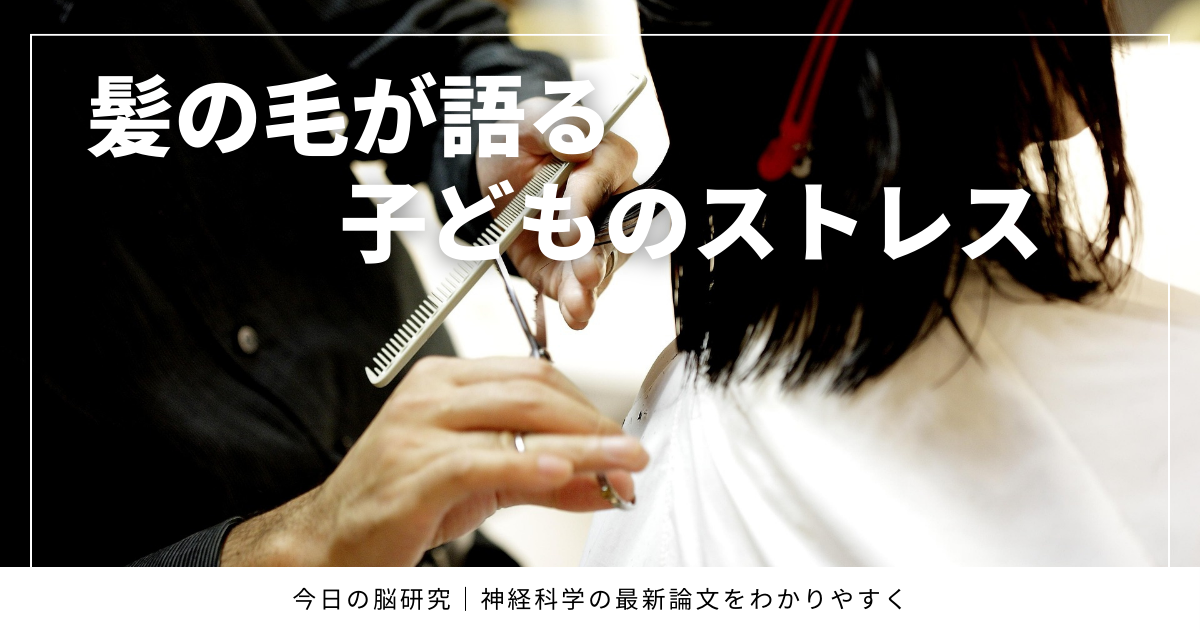


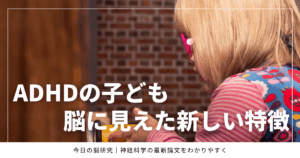
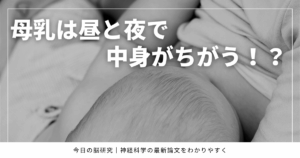
コメント