こんにちは、Dayです!
このブログでは、最新の脳科学論文を一般の方にも楽しめるようにわかりやすくまとめています。
今回のテーマは「AIで明らかになった新しい性格の構造」についてです。
15万人以上の回答データを分析した結果、従来のビッグファイブでは見えなかった性格の特徴が浮かび上がってきました。
「外向性」や「誠実性」といった5つの大きな枠組みはこれまで心理学の基本とされてきましたが、最新の分析ではその間に「社交性」や「衝動性」「誠実さ」などの新しい側面が見えてきたのです。
さらに、AIを活用した手法によって、性格がまるで階層的な地図のように整理できることも示されました。
この記事では、研究が明らかにした新しい性格の構造と、その科学的なおもしろさをわかりやすく紹介します。
あなたの「知られざる性格の顔」が、この研究から見えてくるかもしれません。
本記事は、以下の研究をもとにしました。
Samo, A., Garrido, L. E., Abad, F. J., Golino, H., McAbee, S. T., & Christensen, A. P. (2025). Revisiting the IPIP‑NEO Personality Hierarchy with Taxonomic Graph Analysis. European Journal of Personality. Advance online publication.
https://doi.org/10.1177/08902070251352590
ビッグファイブとは?性格を理解するための5つの柱
私たちの性格は複雑で、人によって「社交的」「几帳面」「おおらか」など、さまざまな特徴があります。心理学では、この性格を大きく整理するための代表的な理論としてビッグファイブ(五因子モデル)が使われてきました。
ビッグファイブは、人の性格を以下の5つの柱に分けて理解しようとする考え方です。
- 外向性(Extraversion):明るく社交的か、それとも控えめで内向的か
- 協調性(Agreeableness):思いやりがあり人と調和しやすいか、それとも自分の主張を優先しがちか
- 誠実性(Conscientiousness):計画的で責任感があるか、それとも気分に流されやすいか
- 神経症傾向(Neuroticism):不安や緊張を感じやすいか、それとも落ち着いて安定しているか
- 開放性(Openness):新しい体験やアイデアに柔軟か、それとも保守的で変化を好まないか
この5つは世界中で多くの研究によって確認されており、性格診断テストや就職活動の適性検査、カウンセリングの場面などでも広く使われています。
言い換えれば、ビッグファイブは「性格をシンプルに説明するための地図」。
ただし、この“5つの柱”で本当に人間の性格すべてを語れるのかどうか、近年は議論が続いています。
最新研究の概要|AIで性格を再分析するとどうなる?
「性格は5つで説明できる」という従来の常識に挑んだのが、2025年に発表された最新研究です。研究チームは15万人以上の回答データ(IPIP-NEOテスト300項目)を用い、AIやデータサイエンスの手法を取り入れて性格の構造を再分析しました。
この研究で使われたのは、Taxonomic Graph Analysis(TGA)と呼ばれる新しい分析手法です。従来の因子分析では「最初に5つの因子があるはず」という前提を置くことが多いのに対し、TGAはデータから自然に浮かび上がるパターンを見つけることができます。
つまり、AIを使って「性格の地図を一から描き直す」ようなイメージです。
結果として研究者たちは、これまでのビッグファイブに加えて、「社交性」「衝動性」「誠実さ」などの新しい特性を発見しました。
さらに、性格は単なる5つの枠組みではなく、細かな特徴 → 特性 → メタ特性へとつながる“3階建ての階層構造”を持つことが明らかになったのです。
研究で見えてきた新しい性格の構造
AIによる大規模データの分析から、人間の性格はただ「5つの因子」で表されるだけではなく、階層的な構造を持っていることが明らかになりました。
研究チームは、性格を次のような“3階建ての構造”として整理しています。
🔹 第1レベル:具体的な特徴(ファセット)
日常的な行動や傾向に近い28の細かな性格要素。
例:几帳面さ、活動性、親切さ、想像力など。
🔹 第2レベル:大きな特性(Traits)
これまでのビッグファイブに加え、新しく3つの特性が浮かび上がりました。
- 外向性(Extraversion)
- 協調性(Agreeableness)
- 誠実性(Conscientiousness)
- 神経症傾向(Neuroticism)
- 開放性(Openness)
- 社交性(Sociability) ←新しく見つかった側面
- 衝動性(Impulsivity) ←行動コントロールに関わる側面
- 誠実さ/Integrity ←正直さや一貫性を示す側面
🔹 第3レベル:さらに抽象的な「メタ特性」
複数の特性をまとめる上位のカテゴリー。従来のモデルではあまり注目されなかった、「Disinhibition(非抑制性)」と呼ばれる新しいメタ特性も確認されました。
これは、感情や行動をどれだけ抑えられるか、あるいは衝動に流されやすいかを示す重要な軸です。
なぜ科学的におもしろいのか?
今回の研究が注目されるのは、単に「ビッグファイブを超える新しい因子が見つかった」からだけではありません。
心理学とAI・データサイエンスの融合によって、これまでの常識を揺さぶる発見がなされた点に大きな意味があります。
1. 性格は「5つで十分」ではなかった
ビッグファイブは長年にわたり「性格研究の決定版」とされてきましたが、今回の分析では社交性・衝動性・誠実さといった新しい特性が浮かび上がりました。
これによって「人間の性格はもっと多面的で豊か」ということが科学的に裏づけられたのです。
2. データから自然に浮かぶ“心の地図”
従来の心理学は「5つの因子がある」という前提を置いてデータを解釈していました。
一方で今回の手法(TGA)は、AIが15万人分のデータをもとに“自然に現れるつながり”を描き出すというアプローチ。
これは「仮説ありき」ではなく、データが教えてくれる新しい発見という点で科学的にとても新鮮です。
3. 人間理解の可能性が広がる
新しい性格の構造を知ることで、心理学だけでなく、教育・職場・メンタルヘルスなど日常生活に直結する応用が期待できます。
例えば「衝動性」の高さは依存症やリスク行動に関係し、「社交性」は対人関係や幸福感に影響するかもしれません。
この研究は「AIが人間の性格を新しい角度から照らし出した」という点で、科学として非常におもしろく、今後の社会や実生活にも広がりをもたらす可能性があるのです。
日常生活へのヒント|この研究から何が学べる?
最新研究が示したのは、性格が「5つの因子」だけでは語れないということ。では、私たちの日常にどんなヒントがあるのでしょうか。
1. 自分の性格を「多面的」にとらえる
「私は外向的だから」「几帳面じゃないから」と、性格を単純に一言で片づけてしまうことはありませんか?
今回の研究が示すように、性格には社交性・衝動性・誠実さなど、より細かな側面があります。
そのため、自分を「一面的」に決めつけるのではなく、「多面的な要素の組み合わせ」として理解することが、自己理解を深める第一歩になります。
2. 他人との違いを受け入れやすくなる
人間関係で「なぜあの人はすぐ衝動的に動くのか?」と感じることもあるでしょう。
でも、この研究からわかるのは「それも一つの性格の特性」だということ。
「人はそれぞれ異なる因子のバランスで成り立っている」と知ることで、相手を理解しやすくなり、人間関係のストレスを減らせます。
3. 自己成長や習慣づくりに役立つ
もし自分に「衝動性」が強いと気づいたら、それを抑える工夫をすれば良いし、「誠実さ」が高ければ計画的に行動する強みとして活かせます。
性格の階層的な理解は、自分の弱点を補い、強みを伸ばす指針になります。
この研究は「性格は5つに分類するもの」という枠を超えて、自分や他人をもっと立体的に理解するヒントを与えてくれるのです。
まとめ|ビッグファイブを超える新しい性格の地図
人の性格は長らく「ビッグファイブ(五因子モデル)」で説明されてきました。
外向性・協調性・誠実性・神経症傾向・開放性という5つの柱は、心理学や日常の性格診断で定番の枠組みです。
しかし今回の最新研究は、AIを活用して15万人以上のデータを分析することで、これまで見過ごされてきた「社交性」「衝動性」「誠実さ」といった新しい特性を明らかにしました。さらに、性格は細かな特徴から大きな特性、そしてメタ特性へと広がる“3階建ての地図”のように構造化されていることが示されたのです。
この成果は、性格を理解する方法がより立体的で柔軟になっていくことを意味します。
「人の性格は5つに収まらない」――この気づきは、自己理解を深めたり、他人を受け入れる視点を広げたりする大きなヒントになるでしょう。
心理学とAIが出会うことで、人間の心の地図はこれからも描き直され続けていきます。
次に見えてくるのは、きっと私たち自身もまだ気づいていない「新しい自分の顔」なのかもしれません。

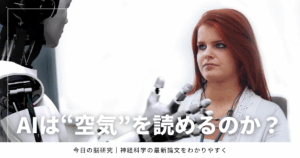

コメント