こんにちは、Dayです!
このブログでは、最新の脳科学論文を一般の方にも楽しめるようにわかりやすくまとめています。
今回のテーマは「お酒と認知症の意外な関係」についてです。
「少しのお酒は健康に良い」とよく耳にしますが、本当にそうなのでしょうか?
最新の国際研究では、これまで言われてきた“軽い飲酒のメリット”が、実は勘違いかもしれないことが明らかになってきました。
観察研究では「少量ならリスクが低い」という結果が見える一方で、遺伝子を使った解析では「飲めば飲むほど認知症のリスクが上がる」というまったく違う結論に。
この記事では、その科学的背景と「なぜ研究ごとに結果が違うのか」をわかりやすく解説し、私たちが日常の飲酒習慣をどう考えるべきかを探ります。
本記事は、以下の研究をもとにしました。
Topiwala, A., Levey, D. F., Zhou, H., Deak, J. D., Adhikari, K., Ebmeier, K. P., Bell, S., Burgess, S., Nichols, T. E., Gaziano, M., Stein, M., & Gelernter, J. (2025). Alcohol use and risk of dementia in diverse populations: Evidence from cohort, case-control and Mendelian randomisation approaches. BMJ Evidence-Based Medicine. Advance online publication.
https://doi.org/10.1136/bmjebm-2025-113913
「少量の飲酒は健康にいい」って本当?
「お酒は少しなら体に良い」と耳にしたことはありませんか?
ワインやビールを少量たしなむと、心臓病や認知症のリスクが下がる──そんな話題はこれまで多くの研究やメディアで紹介されてきました。
実際、観察研究では「お酒を飲まない人」と比べて「少し飲む人」の方が健康リスクが低いように見える結果が何度も報告されています。このため、「少量の飲酒はむしろ長生きにつながるのでは?」と信じられてきたのです。
しかしここで注意したいのは、こうした結果が必ずしも「因果関係」を示しているわけではないという点です。
たとえば、すでに健康を害してお酒をやめた人や、認知機能が低下し始めて飲酒を控えた人が「非飲酒者」に分類されてしまうと、飲まない人の健康リスクが高く見えてしまいます。これを「逆因果」と呼びます。
つまり、「少量の飲酒は健康にいい」という考え方は、統計上の見かけの効果にすぎない可能性があるのです。
なぜ“少量の飲酒は認知症予防に良い”と言われてきたのか
認知症は世界的に患者数が増えており、予防のために「生活習慣との関係」が大きな注目を集めています。その中でも特に関心が高いのがお酒(アルコール)と認知症リスクの関係 です。
これまでの観察研究では、「まったく飲まない人」よりも「少量のお酒を飲む人」の方が認知症になりにくい、という結果が繰り返し報告されてきました。グラフにすると、非飲酒者と大量飲酒者のリスクが高く、少量飲酒者でいちばん低くなる「U字型」や「J字型」のカーブを描きます。
このことから「ワインを1日1杯なら脳に良い」といったイメージが広がり、実際にメディアでも「適度な飲酒は健康にプラス」と取り上げられることが少なくありませんでした。
しかし本当にそうでしょうか?
「お酒をやめた理由」や「健康状態の違い」が研究結果に影響している可能性があるため、科学者たちは慎重に議論を続けてきました。
今回紹介する研究は、この長年の“謎”を解くために、観察研究に加えて 遺伝子を使った因果推定 という新しい手法を組み合わせて調べた点が大きな特徴です。
大規模データと遺伝子解析で“お酒と認知症”を徹底検証
今回の研究の大きな強みは、2つの異なる方法を組み合わせて調べたことです。
- 観察研究(コホート・ケースコントロール)
アメリカやイギリスの大規模データ(50万人以上)を使い、飲酒量と認知症リスクの関係を追跡。
これまでの研究と同じ方法ですが、対象が非常に多いのが特徴です。 - メンデルランダム化(Mendelian randomisation, MR)
お酒の飲み方に影響する遺伝子の違いを手がかりに、アルコール摂取と認知症の因果関係を調べる最新手法。
遺伝子は生まれつき決まっているため、「健康だからお酒をやめた」といった後天的な要因に左右されにくいという利点があります。
このように「観察研究」と「遺伝子解析」という2つのアプローチを比較することで、これまでの『少量飲酒は有利』という結果が本当に正しいのか? をより厳密に確かめようとしたのです。
“少量は有利”に見える観察研究と、“飲むほどリスク増”を示す遺伝子解析
この研究では、観察研究と遺伝子解析でまったく違う結果が出ました。
観察研究の結果
- データを分析すると「少量飲酒者は認知症リスクが低い」という U字型の関係 が見えました。
- 一方で、大量に飲む人やアルコール依存症の人では、明らかに認知症リスクが高まっていました。
- この結果だけを見ると「やっぱり少しならお酒は体に良いのかも?」と思えます。
遺伝子解析の結果
- 遺伝子を使った解析では、飲酒量が増えるほど認知症リスクが直線的に高まる という結果が出ました。
- つまり「少量飲酒が有利」という保護効果は確認されず、むしろ「飲めば飲むほど脳に悪影響がある」と考えられるのです。
なぜ結果が違うのか?
- 観察研究では「すでに体調を崩してお酒をやめた人」や「認知機能が下がって飲酒を控えた人」が“非飲酒者”に含まれてしまうことがあります。
- そのため「飲まない人の方がリスクが高い」という“逆因果”が起き、少量飲酒が良さそうに見えてしまうのです。
なぜ研究の方法で結論が変わるのか?
今回の研究が興味深いのは、同じテーマでも手法によって結論がまったく違ったことです。
- 観察研究では「少量のお酒は認知症リスクを下げるように見える」
- 遺伝子解析では「お酒は少しでも飲めばリスクが増える」
という真逆の結果になりました。
この食い違いは、科学の奥深さを示しています。
観察研究は「現実の生活をそのまま追いかける」ため人数を多く集めやすい一方で、生活習慣や健康状態といった 交絡因子(まぎれ込む要素) の影響を受けやすいという弱点があります。
一方、遺伝子解析(メンデルランダム化)は「生まれつきの遺伝子の違い」を利用するため、交絡や逆因果の影響を減らして因果関係に迫れるのが強みです。
つまりこの研究は、「見かけの関連」と「本当の因果関係」を区別する工夫」 がどれほど重要かを教えてくれるのです。
そして、私たちが日常で耳にする「お酒は体にいいらしい」という情報の裏に、複雑な科学的背景が隠れていることを示しています。
“少量なら安心”は本当?健康へのメッセージ
今回の研究から見えてきたのは、「少量の飲酒は脳に良い」という神話は、科学的には裏付けが弱いということです。
観察研究では一見「少し飲むと認知症リスクが下がる」ように見えますが、それは 体調を崩して飲酒をやめた人 が“飲まない人”に含まれていた可能性が高いのです。
遺伝子解析では逆に、飲酒量が増えるほどリスクが高まる という結果が出ており、「お酒は少しでも無害とは言えない」ことが示唆されました。
では私たちはどう考えればいいのでしょうか?
- 「毎日の一杯は健康にいい」という理由で飲むのは避ける
- 楽しみとして飲む場合も、量をできるだけ減らすことが脳の健康につながる
- 認知症予防の観点からは、お酒以外の生活習慣(運動・睡眠・食事)に注目するのが賢い選択
つまり、「お酒は適度なら大丈夫」と思い込むのではなく、“少ないほど安心”という視点で見直すことが大切なのです。
まとめ|お酒と認知症リスクをどう考える?
- これまでの観察研究では「少量のお酒は認知症リスクを下げる」ように見えていました。
- しかし今回の大規模研究と遺伝子解析では、飲酒量が増えるほどリスクが高まる という結果が示されました。
- 観察研究の「少量有利」という結果は、健康を崩してお酒をやめた人が含まれていた可能性が高く、見かけの効果にすぎないと考えられます。
つまり、 科学的に確かなのは「お酒は少ないほど脳に安心」ということ。
「毎日1杯は健康にいい」といった言葉に惑わされず、認知症予防のためには飲酒量をできるだけ減らすことが勧められます。
そして、お酒以外の生活習慣(運動・睡眠・バランスの良い食事)が、脳の健康を守る確かな方法であることも忘れてはいけません。
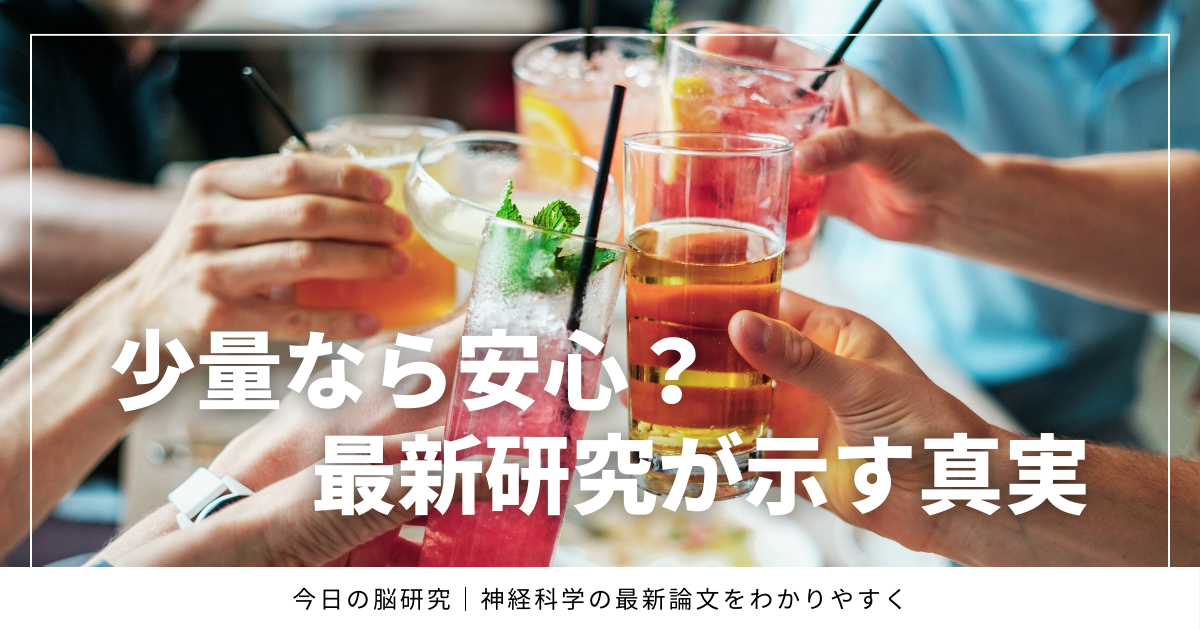

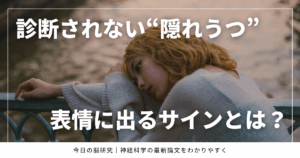
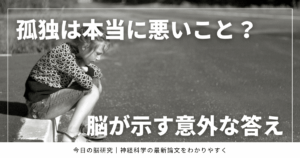
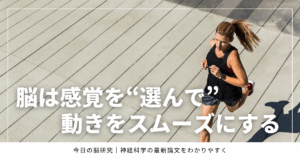

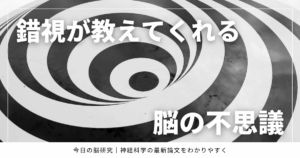
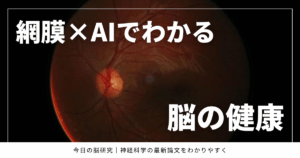
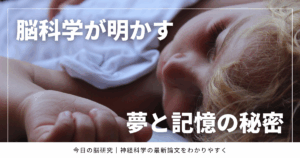
コメント