こんにちは、Dayです!
このブログでは、最新の脳科学論文を一般の方にも楽しめるようにわかりやすくまとめています。
今回は「昼と夜で中身が違う母乳の最新研究」です。
母乳は赤ちゃんにとって最高の栄養源といわれますが、実はその“中身”は一日中同じではありません。
最新の研究によると、母乳には昼と夜で異なるホルモンや免疫成分、さらには細菌が含まれており、赤ちゃんの体内時計や睡眠、成長のリズムをサポートしていることが明らかになってきました。
今回は、この驚きの発見をわかりやすく解説しながら、日常の子育てにどう役立つのかを紹介していきます。
本記事は、以下の研究をもとにしました。
Jiang, Y., Xu, Y., Tian, J., Wu, H., Chen, Y., Pan, L., Sun, J., Li, L., Yang, C., & Chen, Z. (2025). Day/night fluctuations of breast milk bioactive factors and microbiome. Frontiers in Nutrition, 12:1618784.
https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1618784
母乳は昼と夜でどう変わる?
母乳は赤ちゃんにとってただの「栄養ドリンク」ではなく、時間帯によってその中身が変わることが研究でわかってきました。
たとえば、夜の母乳には眠りを促すホルモン「メラトニン」が多く含まれ、赤ちゃんがスムーズに眠りやすくなるサポートをしています。一方で、朝や昼の母乳には「コルチゾール」という目覚めや代謝を助けるホルモンが多く含まれ、赤ちゃんの活動を後押ししています。
さらに、免疫を守る抗体や腸の発達を助ける成分の量も、昼と夜で違いがあることが確認されています。
こうした成分の変化は、赤ちゃんの睡眠リズムや体内時計を整えるための「自然からの仕組み」だと考えられています。
つまり母乳は、赤ちゃんの成長や生活リズムに合わせて“24時間対応”で働いている、とても不思議で頼もしい存在なのです。
母乳と赤ちゃんの体内時計の関係
赤ちゃんは大人のようにしっかりとした体内時計を持って生まれてくるわけではありません。
昼と夜の区別がつきにくく、夜中に何度も目を覚ますのはそのためです。ここで重要な役割を果たしているのが、母乳に含まれる「時間のメッセージ」ともいえる成分です。
たとえば、夜の母乳に多く含まれるメラトニンは、赤ちゃんに「今は寝る時間だよ」というサインを送ります。逆に、朝から昼にかけて増えるコルチゾールは、赤ちゃんの目覚めや活動を助ける働きがあります。こうした昼夜での成分の変化が、赤ちゃんの体内時計を少しずつ整え、日中は活動的に、夜はしっかり眠れるリズムづくりにつながっているのです。
さらに、研究ではこの成分の変動が赤ちゃんの月齢によっても変わることが示されています。生まれてすぐの時期にはあまりはっきりしないのですが、生後1〜6か月の間に昼夜のメリハリが大きくなり、リズム形成をサポートしていると考えられています。
母乳はただの栄養ではなく、赤ちゃんの「時計合わせ」を手助けする大切な役割を担っているのです。
母乳に含まれる免疫成分と腸内環境
母乳は赤ちゃんの「最初のワクチン」とも呼ばれるほど、免疫を支える成分が豊富に含まれています。
その代表がIgA(免疫グロブリンA)とラクトフェリンです。IgAは病原体から赤ちゃんを守り、感染症のリスクを減らす働きをします。ラクトフェリンは鉄と結びついて有害な菌の増殖を抑えるだけでなく、腸内で善玉菌が育ちやすい環境をつくることも知られています。
さらに最新の研究では、母乳に含まれる細菌(マイクロバイオーム)にも昼と夜で違いがあることが示されました。夜の母乳には皮膚由来の細菌が多く、朝の母乳では環境由来の細菌が目立つなど、時間帯によって“母乳の中の生き物たち”も入れ替わっているのです。これらの細菌は赤ちゃんの腸内に入り込み、消化や免疫の発達をサポートします。
つまり、母乳は単なる栄養ではなく「免疫システムの先生」であり、「腸内環境のデザイナー」でもあります。昼と夜で成分や細菌が変わることで、赤ちゃんはより効率的に免疫を育て、健康的な腸内環境を整えているのです。
子育てへのヒント ― 搾乳と授乳の工夫
母乳が昼と夜で中身を変えていることを踏まえると、ちょっとした工夫で赤ちゃんの生活リズムをサポートできる可能性があります。
たとえば搾乳をして保存する場合、昼に搾った母乳は昼に、夜に搾った母乳は夜に与えるように意識してみると、体内時計に沿った自然なリズムづくりにつながるかもしれません。
また、夜の母乳には眠りを助ける成分が多いため、夜泣きや寝つきに悩むときに「夜用の母乳」をしっかり活用することが、赤ちゃんの睡眠改善に役立つ可能性があります。
反対に、日中の母乳は赤ちゃんの活動を後押しする成分が豊富なので、起きて遊ぶ時間に与えると、より元気に過ごせるでしょう。
もちろん、すべての授乳を厳密に分ける必要はありません。赤ちゃんの個性や家庭のライフスタイルに合わせて、「なんとなく意識してみる」だけでも十分です。母乳の不思議な“時間差サポート”を味方につけることで、育児が少し楽になり、赤ちゃんも心地よいリズムを身につけていけるのです。
まとめ ― 昼夜で変わる母乳の科学と子育ての未来
母乳は赤ちゃんにとって最高の栄養源であると同時に、昼と夜でその中身を変えながら、体内時計や免疫、腸内環境を整える役割を果たしていることが研究で明らかになってきました。
夜には眠りを促す成分が増え、昼には活動を助ける成分が多いという仕組みは、まさに「自然からのギフト」といえるでしょう。
子育ての現場では、搾乳のタイミングや授乳の工夫に活かせる可能性がありますし、将来的には母乳成分の時間変化を応用したミルク製品や育児サポート方法が登場するかもしれません。
こうした科学の発見は、母乳を与えることに安心感を与えるだけでなく、「赤ちゃんのリズムを母乳が一緒に育てている」という新しい視点を届けてくれます。日々の授乳を通じて、母乳が持つ奥深い力を感じながら、赤ちゃんとともに健やかな未来を育んでいきたいですね。
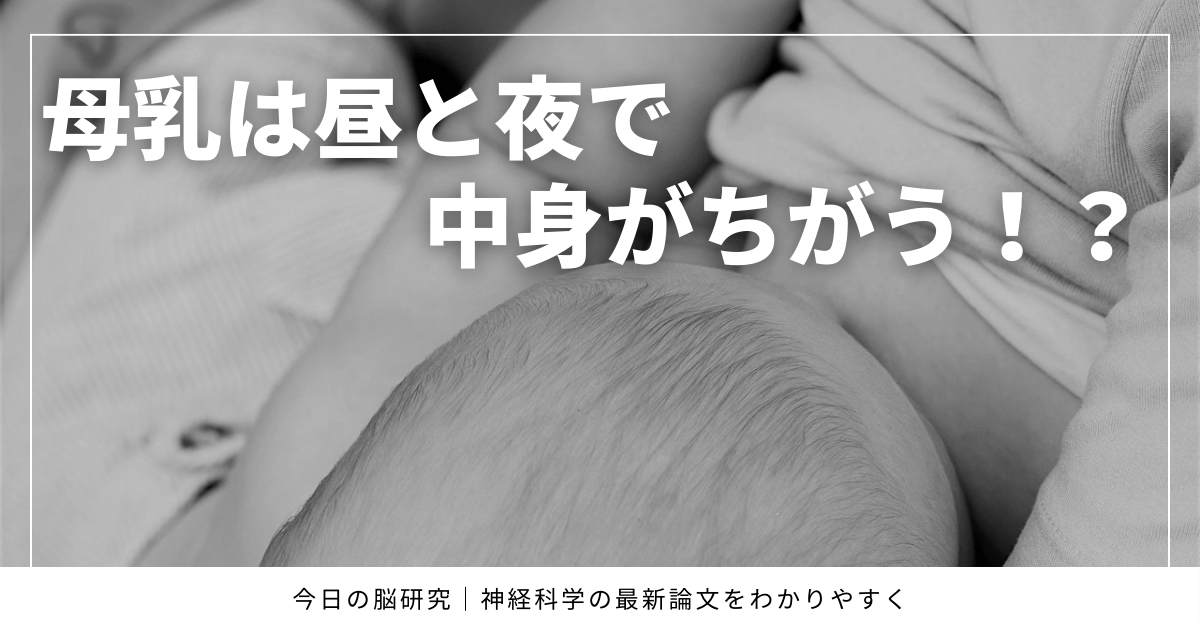

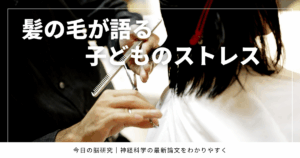

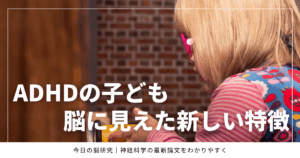
コメント