こんにちは、Dayです!
このブログでは、最新の脳科学論文を一般の方にも楽しめるようにわかりやすくまとめています。
今回のテーマは「犬は人間の言葉をどこまで理解できるのか?」についてです。
私たち人間は「ボール」や「椅子」といった言葉を聞くと、その形や色だけでなく、「投げて遊ぶもの」「座るもの」といった“役割”まで自然に理解しています。では、犬はどうでしょうか? 単に「丸い物体=ボール」と認識しているのか、それとも「一緒に遊ぶもの=ボール」と機能で理解しているのか。
最新の研究では、特別に訓練された犬ではなく、日常生活の中で多くの単語を学んだ犬を対象に実験を行い、犬が言葉を“カテゴリー化の道具”として使えるかどうかを検証しました。
その結果は、「犬の言葉理解は想像以上に深いかもしれない」という驚きの内容。
愛犬と暮らす人にとっても、「うちの子はどこまで理解しているの?」と気になる視点がたくさん詰まった研究です。
本記事は、以下の研究をもとにしました。
Fugazza, C., Sommese, A., & Miklósi, Á. (2025). Dogs extend verbal labels for functional classification of objects. Current Biology. Advance online publication.
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(25)01079-6
犬は人間の言葉をどこまで理解できる?
「おすわり」「お手」といった指示語を理解する犬は多いですが、実際にどのくらい人間の言葉を理解しているのかは、長年の疑問でした。単に音のパターンを覚えて反応しているだけなのか、それとも言葉の“意味”まで理解しているのか――。
今回の研究では、この問いに対してユニークな切り口で挑みました。犬が「ボール」という言葉を聞いたとき、それを“丸い形のもの”として認識しているのか、それとも“投げて遊ぶ道具”として捉えているのかを検証したのです。
もし犬が形ではなく「役割」に基づいて言葉を理解しているとすれば、それは人間の幼児の言語発達と似た特徴を持っていることを意味します。つまり犬は、単なる条件反射ではなく、言葉を通じて世界をカテゴリー化する力を持っている可能性があるのです。
最新研究が明らかにした犬の“言葉の使い方”
この研究では、特別に訓練された犬ではなく、飼い主との日常生活の中で自然に多くの単語を覚えた犬を対象にしました。つまり「普通の家庭犬」が、どのように言葉を理解しているのかを明らかにする実験です。
研究チームは、犬に対して「ボール」や「ロープ」といった言葉を提示し、実際にどの物を選ぶのかを観察しました。その際に注目したのは、犬が形の似ている新しい物を選ぶのか、それとも機能が同じ新しい物を選ぶのか、という点です。
結果として、一部の犬は「形」ではなく「機能」に基づいて物を選ぶ傾向を示しました。たとえば「ボール」という言葉を聞いた犬が、見たことのない形のボールでも「投げて遊べるもの」として認識し、正しく選び取ったのです。
この発見は、犬が言葉を「音とモノの対応」として覚えるだけではなく、「役割や用途」という抽象的な概念にまで結びつけている可能性を示しています。これは、動物の言語理解研究において大きな一歩といえるでしょう。
犬が言葉をカテゴリー化できるってどういうこと?
「カテゴリー化」とは、モノや出来事を“ひとまとめ”に理解することを指します。人間の幼児は成長の中で、「ボール」と聞けばサッカーボールやテニスボールなど形が違っても「遊ぶ道具」としてひとつのカテゴリーに入れて理解します。これは言葉を学ぶうえでとても重要な能力です。
今回の研究は、犬も同じように言葉をカテゴリー化の道具として使えるのかどうかを検証しました。もし犬が「ボール=丸いもの」とだけ理解しているなら、見慣れない形のボールには反応できません。しかし「ボール=投げて遊ぶもの」と理解していれば、見たことのないデザインでも正しく判断できるはずです。
つまり、犬が言葉をカテゴリー化できるということは、単なる条件反射を超えて、“抽象的な意味”をくみ取る力を持っていることを示しています。これは動物の知能研究においても非常に大きな発見であり、人間とのコミュニケーションの理解を深めるヒントにもなります。
飼い主にとっての意味 ― 愛犬は何を理解しているのか
この研究は、単なる学術的な発見にとどまりません。私たち飼い主にとっても、「犬はどこまで言葉を理解しているのか?」という永遠のテーマに新しい視点を与えてくれます。
たとえば、犬に「ボール持ってきて」と声をかけるとき、犬は単に“見慣れた丸いおもちゃ”を探しているのではなく、“一緒に遊べる道具”として理解している可能性があります。もしそうであれば、私たちが使う言葉には、犬の行動や感情をより豊かに引き出す力があるといえるでしょう。
また、「散歩」「ごはん」といった日常の単語も、犬にとってはただの音ではなく、“行動の予告”や“楽しい出来事の合図”として理解されているかもしれません。こうした認識を踏まえると、私たちは犬とのコミュニケーションをもっと意識的に工夫できるようになります。
つまり、この研究は「犬は言葉をどこまで理解しているのか?」という問いに答えるだけでなく、「飼い主としてどう向き合えば、もっと通じ合えるのか?」という実践的なヒントをも与えてくれるのです。
まとめ|犬は言葉を「意味」で理解する時代へ
今回紹介した研究は、犬が人間の言葉を「音と物の単純な対応」としてだけでなく、機能や役割に基づいて理解している可能性を示しました。これは、犬が人間の幼児と同じように、言葉をカテゴリー化の道具として使えるかもしれないという、非常に興味深い発見です。
この成果は、学術的な視点からは「動物の言語理解」に新たな一歩をもたらすと同時に、飼い主にとっては「愛犬は私の言葉をどう受け取っているのか?」という日常的な疑問への答えにもつながります。
今後さらに研究が進めば、犬とのコミュニケーションはこれまで以上に豊かになり、単なる命令やしつけを超えて、「意味を共有するパートナー」としての関係が深まっていくでしょう。
愛犬の瞳の奥には、私たちが想像する以上に“ことばの世界”が広がっているのかもしれません。

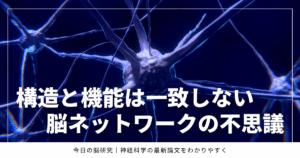
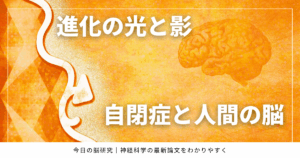
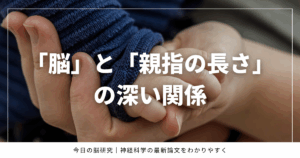
コメント