こんにちは、Dayです!
このブログでは、最新の脳科学論文を一般の方にも楽しめるようにわかりやすくまとめています。
今回のテーマは「胎動が母子の絆を育む科学的な仕組み」についてです。
妊娠後期になると赤ちゃんの動きを感じる機会が増え、「元気に動いていて安心した」「今日はよく動くな」と思うママも多いでしょう。
実はこの胎動は、赤ちゃんの健康のサインであるだけでなく、母親の心に“愛着”を育てる大切な役割を持つことが最新研究で明らかになりました。
今回は、胎動と母子の愛情のつながりを科学的に解き明かした論文をご紹介しながら、妊娠中の体験がどのように未来の親子関係につながっていくのかをわかりやすく解説します。
本記事は、以下の研究をもとにしました。
Ayala, K., Falcioni, L., Eilbott, J., Lamore, J., Voegtline, K., & Rutherford, H. J. V. (2025). Associations between fetal movement and maternal–fetal attachment in late pregnancy. Early Human Development, 196, 106351.
https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2025.106351
胎動とは?妊娠後期に感じる赤ちゃんのサイン
胎動(たいどう)とは、お腹の中で赤ちゃんが動くことを指します。
多くの妊婦さんは妊娠20週前後から胎動を感じ始め、妊娠後期に入るとその動きがよりはっきりしてきます。お腹の中で「ポコッ」と蹴られる感覚や、ぐるっと回転するような大きな動きは、妊娠を経験した方なら一度は実感したことがあるでしょう。
妊娠後期になると赤ちゃんはぐんと大きく成長し、子宮内のスペースが限られてくるため、動き方も変化してきます。ドシンと強い蹴りや手足の突き出しを感じることもあれば、体勢を変えるときにお腹全体がグッと押されるような感覚を覚えることもあります。
胎動は「赤ちゃんが元気に育っているサイン」として医学的にも重視されています。妊婦健診でも胎動について質問されるのはそのためです。ただ、それだけではなく、胎動は母親にとって「赤ちゃんの存在を実感できる貴重な瞬間」でもあります。まだ会ったことのないわが子を身近に感じる体験こそが、母と子の絆の始まりだと言えるのです。
胎動と母子の愛着の関係 ― 最新研究からわかったこと
「胎動を感じると赤ちゃんが愛おしくなる」という体験談は多くの妊婦さんから聞かれます。
では、それは単なる気持ちの問題なのでしょうか?最新の科学研究は、胎動と母親の愛着形成に本当に関係があることを示しています。
2025年に発表された研究では、妊娠後期の妊婦さん51人を対象に、胎児の動きを客観的に計測できる機器を使い、その動きの量と母親が赤ちゃんに抱く「愛着(母性‐胎児愛着)」との関係を調べました。すると、胎動が多いほど母性‐胎児愛着スコアが高いことが分かったのです。
この結果は、母親が「動いた」と感じる主観だけではなく、実際の赤ちゃんの動きそのものが母親の気持ちを育てていることを意味します。つまり、胎動は赤ちゃんが元気に成長しているサインであると同時に、母と子の心を結ぶ“架け橋”としての役割も果たしているのです。
なぜ赤ちゃんの動きが母親の気持ちを育てるのか
お腹の赤ちゃんの動きは、ただの身体的な現象ではありません。最新研究によれば、その一つひとつの動きが、母親の「赤ちゃんへの愛情」や「絆」を強める大切な役割を果たしています。
では、なぜ胎動が母親の気持ちを育てるのでしょうか?
- 赤ちゃんの存在を実感できるから
胎動は「ここに赤ちゃんがいる」という確かなサインです。動きを感じるたびに、母親は赤ちゃんの存在をリアルに意識しやすくなり、自然と愛着が深まっていきます。 - 脳が“母性モード”に切り替わるから
研究では、胎動を感じたとき母親の脳では感情や共感に関わる領域が活性化することが示されています。これは、赤ちゃんの動きが母親の脳にポジティブな刺激を与え、愛情や保護本能を育てるスイッチになっていると考えられます。 - コミュニケーションの第一歩になるから
「蹴られたからお腹をさすった」「動いたから話しかけてみた」という経験は、まだ言葉を持たない赤ちゃんとの“対話”の始まりです。母親の反応に応えるように再び動くこともあり、これがさらに絆を深めていきます。
こうした理由から、胎動は単なる生理的現象を超えて、母と子の最初のコミュニケーションとも言えるのです。
妊娠中にできる!胎動を通じた母子の絆づくり
胎動は自然に起こるものですが、意識の仕方次第で母子の絆をより深めることができます。妊娠中の毎日で取り入れやすい工夫をいくつかご紹介します。
- 胎動を日記につける
「今日は何回くらい動いた」「夜によく動いていた」など、簡単にメモを残すだけでも赤ちゃんとのつながりを感じやすくなります。振り返ることで成長の記録にもなります。 - 動きを感じたら声をかける
お腹をトントンとさすりながら「元気だね」「おはよう」と声をかけてみましょう。実際に赤ちゃんが反応することもあり、コミュニケーションの第一歩になります。 - パートナーや家族と一緒に感じる
胎動を家族と共有することで、母親だけでなく周囲の人も赤ちゃんの存在を身近に感じられます。父親やきょうだいにとっても愛着形成のきっかけになります。 - 安心できるリラックスタイムを持つ
ストレスや不安が強いと胎動を感じにくいこともあります。リラックスした時間をとることで、赤ちゃんの動きにも気づきやすくなり、心穏やかに向き合えるようになります。
胎動は医学的には赤ちゃんの健康状態を知るサインでもありますが、同時に「母と子の心をつなぐ大切な時間」でもあります。少しの工夫で、その体験をより豊かなものにしていきましょう。
この研究が示す今後の可能性
今回の研究は、「胎動が母性‐胎児愛着を育む」ということを科学的に示した点で大きな意義があります。さらに、この知見は今後の妊婦ケアや育児支援に広く応用できる可能性を秘めています。
- 出産後の親子関係への影響
妊娠中に形成された愛着は、出産後の母子関係や育児のあり方に影響します。胎動を意識して過ごした妊婦さんは、赤ちゃんとの絆をすでに築き始めているため、育児の初期段階でスムーズに愛着を育てやすいと考えられます。 - 心理的支援の新しいアプローチ
妊娠中に不安や抑うつを抱える女性は少なくありません。胎動を活用したケア(胎動日記、声かけ、リラクゼーションなど)を取り入れることで、心理的安定を促し、愛着形成を支援できる可能性があります。 - 医療・教育現場での情報提供
助産師や医師が「胎動は赤ちゃんの元気の証であるだけでなく、母子の絆を深める大切なサインです」と伝えることで、妊婦さんが前向きな気持ちで妊娠生活を過ごす手助けになります。 - 科学と日常生活の橋渡し
胎児の動きを客観的に測定する研究は進んでいますが、実際の妊婦さんが日常生活の中でどう感じ、どう受け止めるかはまだ発展途上の分野です。今後は科学的な知見と日常の実感をつなげることで、より豊かな妊娠期サポートにつながるでしょう。
このように、胎動研究は単なる医学的データではなく、「母子の絆を科学的に理解し、実生活に役立てる」新しいステップになり得るのです。
まとめ|胎動は母と子の最初のコミュニケーション
胎動は、赤ちゃんが元気に育っていることを知らせてくれる大切なサインであると同時に、母と子の心を結ぶ最初のコミュニケーションでもあります。
今回紹介した研究では、妊娠後期の胎児の動きが多いほど、母親の赤ちゃんへの愛着が強まることが科学的に示されました。これは「赤ちゃんが動く → 母親が存在を実感する → 愛情や絆が深まる」という自然なサイクルを裏付けています。
胎動を感じたときにお腹をさすったり、声をかけたり、家族と共有したりすることは、すでに母子の絆を育む行為のひとつ。つまり、お腹の中の小さな動きが、未来の親子関係の基盤を作っているのです。
これから赤ちゃんを迎える妊婦さんにとって、胎動は単なる生理現象ではなく、愛情を育むかけがえのない時間。日常の中でその瞬間を大切に味わうことが、母と子の幸せなスタートにつながっていきます。

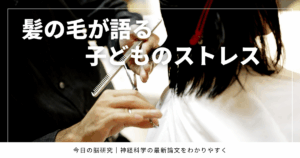

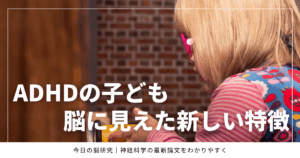
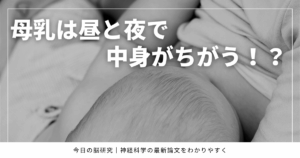
コメント