こんにちは、Dayです!
このブログでは、最新の脳科学論文を一般の方にも楽しめるようにわかりやすくまとめています。
今回のテーマは「錯視がなぜ見えるのか ― 脳が見えない線を描き足す仕組み」についてです。
みなさんは「カンニッツァ三角形」や「だまし絵」を見たことがありますか? 実際には線が描かれていないのに、まるで存在するかのように三角形や輪郭が浮かび上がって見える――これが錯視です。
一見するとただの“目の錯覚”に思えるかもしれません。しかし最新の脳科学研究によって、錯視は単なる勘違いではなく、脳が積極的に世界を“予測”し、“見えない線を描き足している”現象だとわかってきました。
この仕組みを解き明かすことは、「なぜ人間の脳は現実をそのまま写すカメラではなく、想像力を駆使するアーティストのように働くのか?」を理解することにつながります。
また、錯視の研究は将来的に人工知能(AI)の視覚機能の発展や、人間の知覚の仕組みを応用した医療技術にも役立つ可能性があります。
本記事では、最新論文をもとに「なぜ錯視が見えるのか」「脳はどんな仕組みで線を描き足しているのか」を、専門知識がなくてもわかるように解説していきます。
本記事は、以下の研究をもとにしました。
Shin, H., Ogando, M. B., Abdeladim, L., Jagadisan, U. K., Durand, S., Hardcastle, B., … Adesnik, H. (2025). Recurrent pattern completion drives the neocortical representation of sensory inference. Nature Neuroscience.
https://doi.org/10.1038/s41593-025-02055-5
錯視とは? ― 見えない線が見える不思議な現象
「錯視(さくし)」とは、実際には存在しない線や形が、あたかも目の前にあるように見えてしまう現象のことです。
たとえば有名な「カンニッツァ三角形」では、ただの黒い円や線の組み合わせなのに、真ん中に白い三角形が浮かび上がって見えます。実際には描かれていないのに“見える”――これこそが錯視の不思議さです。
多くの人は「目がだまされている」と思いがちですが、実はそうではありません。錯視は目の錯覚というよりも、脳が「ここに線があるはずだ」と予測して描き足してしまう仕組みによって起こります。つまり、錯視は私たちの脳が「現実をそのまま受け取る」のではなく、「想像力を使って補う」ことを示す現象なのです。
錯視はなぜ起こるのか ― 脳が世界を“予測”する仕組み
錯視が起こる理由は、脳が単なるカメラのように現実を映すだけではなく、「これから見えるはずの形」を予測しているからです。私たちの目に映る情報は、いつも完全とは限りません。暗闇や影、物が一部隠れている場面など、欠けた情報をどう補うかが重要になります。
このとき活躍するのが、脳の「パターン補完」と呼ばれる働きです。脳はこれまでの経験や知識をもとに、欠けている部分を自動的に埋め、見えない線を“描き足す”ことで全体の形を理解しようとします。錯視は、この「脳の補完能力」が強く表れてしまう現象なのです。
つまり、錯視は“脳がだまされる”のではなく、“脳が積極的に推理している証拠”ともいえます。世界をそのまま写し取るのではなく、予測と想像を組み合わせて現実を再構築する――この柔軟な仕組みこそ、人間の脳が持つ大きな特徴なのです。
最新研究が解明した「錯視を生み出す神経細胞」
では、脳の中ではどのようにして錯視がつくられているのでしょうか? 最新の脳科学研究によって、実際に「錯視を生み出す神経細胞」が特定されました。
研究では、マウスの脳を詳しく調べたところ、視覚野(V1)の中に「ICエンコーダー」と呼ばれる神経細胞が見つかりました。この細胞は、実際には線が描かれていない場所でも、錯視によって「ここに線がある」と感じるときに活発に働くのです。まるで脳の中で見えない線を描き足している“アーティスト”のような存在です。
一方で、線の一部だけに反応する「セグメント応答細胞」もありました。しかし、これらは錯視そのものをつくるわけではなく、実際に存在する線にしか反応しません。つまり、錯視を“本物の線”として感じさせるのはICエンコーダーの役割であることが示されたのです。
さらに研究チームは、この神経細胞を人工的に刺激すると、実際の線が描かれていなくても脳の中に錯視のパターンが再現されることを確認しました。これは、「錯視は脳が作り出す内部の推理プロセスによって生まれている」という強力な証拠です。
錯視研究からわかる脳のすごさ
錯視の研究から見えてくるのは、脳が単なる受け身のカメラではなく、能動的な“推理マシン”であるという事実です。私たちが物を見るとき、脳はただ光の情報を処理しているのではありません。過去の経験や知識をもとに、「ここにはこんな形があるはずだ」と積極的に未来を予測しているのです。
たとえば、暗い場所で物体が一部しか見えなくても、それを「椅子だ」と認識できるのは、脳が不足した情報を補い、見えない部分を勝手に描き足す力を持っているからです。錯視はその力が強く表れた特別な例であり、脳の柔軟さと創造性を私たちに教えてくれます。
さらにおもしろいのは、こうした脳の仕組みが「だまされやすさ」だけでなく、「生き延びる力」にもつながっていることです。もし脳が与えられた情報しか処理できなければ、影の中の動物や隠れた危険をすぐに察知できません。錯視を生むほどの推理能力こそ、私たちが複雑な環境で生き残るために必要なスキルだったと考えられます。
錯視の科学はどんな役に立つのか?
錯視の研究は「人間の不思議な目の錯覚を解き明かす」だけでなく、さまざまな分野で役立つ可能性を秘めています。
まず期待されているのが、人工知能(AI)への応用です。現在のAIは画像認識に優れていますが、「見えない部分を推測して補う力」はまだ人間ほど得意ではありません。錯視を生み出す脳の仕組みを理解すれば、AIにも「足りない情報を想像で補う能力」を持たせることができ、より人間らしい認識が可能になるでしょう。
次に、医療やリハビリ分野への貢献です。脳がどのように視覚を補完しているのかが分かれば、視覚障害や脳の病気で「ものの見え方」に問題を抱える患者さんへの新しい治療や訓練方法につながります。例えば、失われた視覚情報を脳がどう再構築しているのかを利用すれば、より効果的なリハビリが可能になるかもしれません。
さらに、錯視の知識は日常生活や教育にも役立ちます。子どもに「人間の脳は現実をそのまま写すのではなく、想像で補っているんだよ」と伝えれば、科学への興味や学習意欲を高めるきっかけになるでしょう。
つまり錯視の科学は、脳の不思議を楽しむだけでなく、AIの進化・医療の発展・教育への応用といった幅広い未来を切り開く可能性を持っているのです。
まとめ ― 錯視は脳が描く“もうひとつの現実”
錯視とは、実際には存在しない線や形が見えてしまう不思議な現象です。
本記事で紹介した最新研究により、脳の中に「錯視を生み出す特別な神経細胞」が存在し、見えない線を描き足して世界を補っていることがわかってきました。
この仕組みは、単なる“だまされやすさ”ではなく、脳が予測し、推理し、現実を積極的に再構築する力を示しています。錯視は、脳がいかに柔軟で創造的に働いているかを教えてくれる貴重な現象なのです。
さらに、錯視の科学はAIや医療、教育など幅広い分野に応用できる可能性があります。人間の脳が持つ「見えないものを補う力」を理解することは、未来のテクノロジーや私たちの生活にもつながっていくでしょう。錯視を通して見えてくるのは、脳がただの受け身のカメラではなく、想像力で“もうひとつの現実”を描き出すアーティストであるという事実です。次に錯視の画像を見かけたら、「これは脳が描いたもうひとつの世界なんだ」と考えてみると、より一層科学の面白さを感じられるはずです。
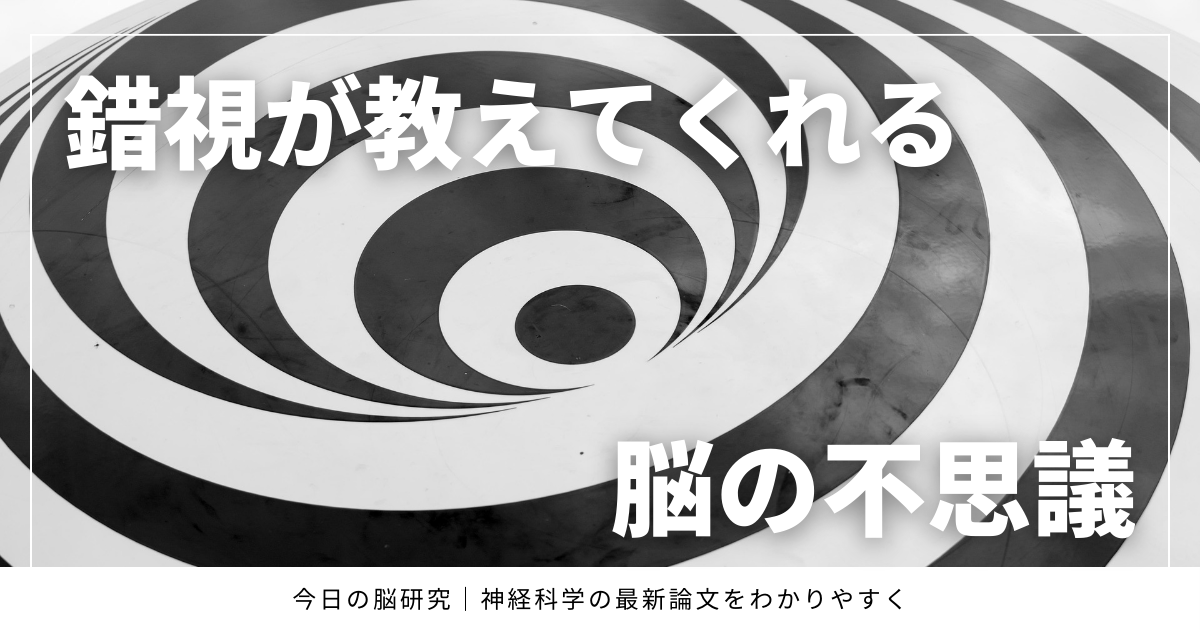

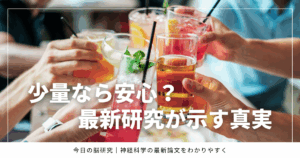
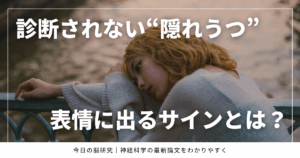
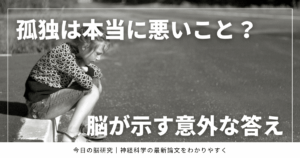
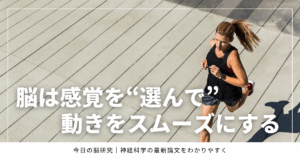

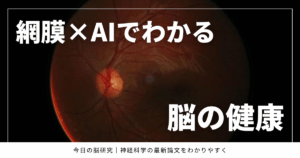
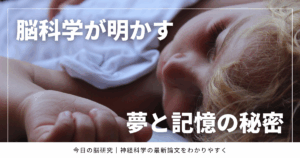
コメント