こんにちは、Dayです!
このブログでは、最新の脳科学論文を一般の方にも楽しめるようにわかりやすくまとめています。
今回のテーマは「雑音の中で声を聞き分けられる人の脳の秘密」についてです。
カフェや居酒屋、教室など、周りがガヤガヤしている場面でも、特定の相手の声をスッと聞き取れる人がいます。逆に、相手の声が雑音にかき消されてしまい、会話がとても疲れる人もいます。
この違いは“耳の良さ”だけではなく、実は知的能力(IQ)と深く関わっていることが最新の研究で明らかになりました。
本記事では、自閉スペクトラム症や胎児性アルコール症候群の方を含む研究から見えてきた「IQと聞き取り力の意外な関係」について、わかりやすくご紹介します。
本記事は、以下の研究をもとにしました。
Lau, B. K., Emmons, K., Maddox, R. K., Estes, A., Dager, S. R., Hemingway, S. J. A., & Lee, A. K. C. (2025). The relationship between intellectual ability and auditory multitalker speech perception in neurodivergent individuals. PLOS ONE, 20(9), e0329581.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0329581
雑音の中で声を聞き分けるのはなぜ難しいのか?
カフェや居酒屋、あるいは学校の教室。周りがざわざわしている状況で、特定の相手の声だけを聞き取るのは意外と大変ですよね。これは脳科学の世界では「カクテルパーティー問題」と呼ばれています。
人の耳は音を正確に拾うだけでなく、脳で「必要な声」と「不要な声」を分ける作業をしています。たとえば、周りで何人も同時に話していても、自分が注目している相手の声を際立たせ、それ以外を背景音として処理するのです。
ところが、この「聞き分け」の作業はとても高度で、単に耳が良いかどうかだけでは決まりません。注意力、記憶力、言語理解力など、脳のさまざまな機能が総動員されるのです。
そのため、雑音の多い場面では、普段よりも脳に負担がかかり、疲れやすくなったり、聞き漏らしたりすることがあります。つまり、「雑音下での聞き取り」は、脳にとってかなりハードなタスクなのです。
今回の研究はどんなことを調べたのか?
今回ご紹介するのは、ワシントン大学を中心に行われた最新の研究です。研究者たちは、「知的能力(IQ)が、雑音の中での聞き取り力にどう影響するのか?」 を調べました。
対象となったのは、
- 自閉スペクトラム症(ASD)の人
- 胎児性アルコール症候群(FASD)の人
- 同年代の健常な比較群
の3グループ、合計49名。全員、聴力検査では「正常な耳」を持っていました。
研究では、参加者に3人が同時に話す状況をシミュレーションして聞かせました。具体的には、
- 正面の「ターゲット話者」の声(例えば「Charlie, go to red five now」)を聞き取る
- 両側から別の人が同時に話す「雑音(マスカー)」を流す
- 参加者はターゲットの「色」と「数字」を正しく答える
というタスクを行いました。
この状況はまさに、カフェや教室などで「一人の声に集中する」場面を再現したものです。研究チームは、この課題でどのくらい正しく答えられるかを指標にして、IQとの関係を分析しました。
研究でわかった意外な結果
実験の結果、もっとも大きな発見は 「IQが高い人ほど、雑音の中での聞き取り力が高い」 という強い関連が見られたことでした。
つまり、耳そのものの性能が同じでも、知的能力の違いが“聞き取り力”を左右していたのです。
IQが高いほど低い声量でも聞き取れる
知能指数が高い人は、ターゲットの声が周囲の声より小さくても正確に聞き取ることができました。逆にIQが低い人は、ターゲットの声がかなり大きくならないと聞き分けられませんでした。
ASDやFASDの人でも同じ傾向
自閉スペクトラム症(ASD)や胎児性アルコール症候群(FASD)のグループでも同じように、IQと聞き取り力の強い相関が確認されました。特に知的障害を持つ人では、雑音下での会話が難しい傾向が顕著に見られました。
言語力だけではなく「総合的な知能」が関与
さらに分析すると、言語能力だけでなく、非言語的な推論力やパズルを解く力なども聞き取り力と関連していました。つまり、単に語彙や言語理解だけではなく、総合的な知能全体が“雑音の中で会話する力”を支えていることがわかりました。
なぜ知能が聞き取り力に関係するのか?
一見すると「雑音の中で声を聞き分ける力」は、耳の性能や音の処理能力だけに左右されるように思えます。ところが今回の研究は、脳の“知能”が大きく関与していることを示しました。
脳は「音の選別」と「意味の理解」を同時に行っている
雑音の中で会話をするとき、脳はまず「この声がターゲットだ」と選び出し、同時にその意味を理解しようとします。この過程には、
- 注意力(集中して一人の声を追いかける力)
- 記憶力(聞いた言葉を一時的に保持する力)
- 推論力(文脈から意味を推測する力)
といった多様な認知機能が総動員されます。
「頭の良さ」が雑音下での聞き取りを助ける
IQが高い人は、これらの認知機能を効率的に使い、雑音の中でも必要な声を浮かび上がらせることができます。逆にIQが低いと、集中や記憶に負担がかかりすぎ、ターゲットの声を見失いやすくなるのです。
言語力だけでは説明できない
さらに重要なのは、語彙力などの「言語的な知能」だけでなく、図形認識や推論といった「非言語的な知能」も聞き取り力に関係していたことです。つまり、雑音下での聞き取りは総合的な知能全体に支えられていると考えられます。
この研究が示す生活へのヒント
今回の研究結果は、私たちの日常生活や教育、支援のあり方に大きなヒントを与えてくれます。
騒がしい教室や職場での学び・仕事
知的能力が低めの子どもほど、騒がしい教室で授業を理解するのが難しい可能性があります。これは「耳の良さ」ではなく、認知的な負担によるものです。学習環境を整えるには、静かな教室や補助的な教材がより重要になるかもしれません。
発達特性のある人への支援
自閉スペクトラム症や胎児性アルコール症候群の人たちは、騒がしい環境で会話するのに苦労しやすいことがわかりました。したがって、支援のあり方も「補聴器」や「静かな場所の提供」だけではなく、認知能力に合わせた工夫(情報の整理、視覚的サポート、話す速度の調整など)が求められます。
「聞き取りが苦手=耳が悪い」ではない
耳の検査では問題がないのに「人の声が聞き取りにくい」と感じる人も少なくありません。この研究は、その背景に知能や脳の認知的な働きがあることを示しています。つまり、「聞き取りが苦手」だからといって、必ずしも耳のせいとは限らないのです。
まとめ|IQと聞き取り力の意外な関係
今回ご紹介した研究では、「雑音の中で声を聞き分ける力」は耳だけではなく、知的能力(IQ)と強く結びついていることが明らかになりました。
- IQが高い人ほど、周囲がうるさい中でも正確に会話を理解できる
- 言語力だけではなく、非言語的な推論力や記憶力など、総合的な知能が関与している
- 発達特性を持つ人にとっても、この関係は同じように見られる
これらの結果は、「聞き取りにくさ」が必ずしも耳の問題ではなく、脳の情報処理や認知の特徴によるものであることを示しています。
日常生活では、カフェや職場、教室など騒がしい場面がたくさんあります。そこでの聞き取りを助けるには、単に環境を静かにするだけでなく、個々の認知的な特性に応じた支援や工夫が大切です。
今回の研究は、「コミュニケーションのしやすさ」を理解する上で新しい視点を与えてくれました。耳と脳がどのように協力して雑音の中から声を拾い上げているのか──今後の研究からさらに多くのヒントが得られることが期待されます。

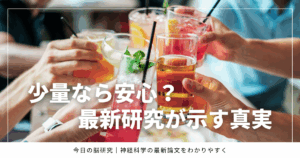
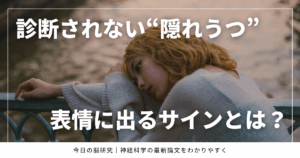
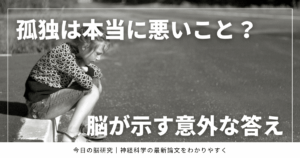
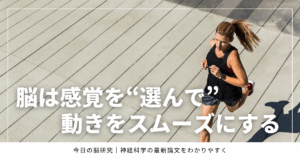

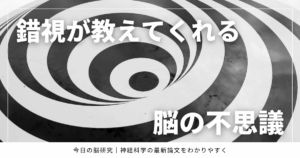
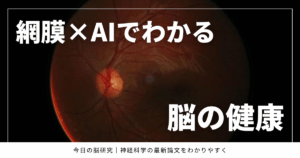
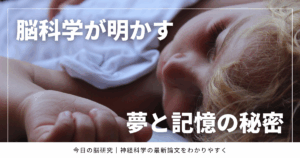
コメント