こんにちは、Dayです!
このブログでは、最新の脳科学論文を一般の方にも楽しめるようにわかりやすくまとめています。
今回のテーマは「授乳期の母親が“攻撃的になる”という現象を、脳とホルモンの働きから解き明かした最新研究」についてです。
普段は穏やかな母マウスが、出産後になると一転して他者に攻撃的になる──そんな行動がどのようにして起こるのか。
スウェーデン・カロリンスカ研究所の研究チームが明らかにしたのは、“眠っていた攻撃回路”が授乳期のホルモンによって一時的に覚醒するという驚きの仕組みでした。
「母性=優しさ」と思われがちな中で、実は脳が“守るために戦う”モードへと切り替わっている。
この研究は、母性の裏に隠れた神経スイッチの存在を、科学的に示した注目の成果です。
本記事は、以下の研究をもとにしました。
Stagkourakis, S., Williams, P., Spigolon, G., Khanal, S., Ziegler, K., Heikkinen, L., Fisone, G., & Broberger, C. (2025). Maternal aggression driven by the transient mobilisation of a dormant hormone-sensitive circuit. Nature Communications, 16(8553).
https://doi.org/10.1038/s41467-025-64043-4
なぜ母親は攻撃的になるのか?──母性行動のもう一つの顔
「母は強し」という言葉には、単なる比喩以上の意味があるのかもしれません。
出産や授乳期の母親が、普段とはまるで別人のように“攻撃的”になることがある──そんな現象は、人間を含む多くの哺乳類で報告されています。
たとえばマウスの世界では、出産後の母親が他の個体(特にオスや他のメス)が巣に近づくと、激しく威嚇したり噛みついたりする行動をとります。これは「母性攻撃(maternal aggression)」と呼ばれ、仔を守るための防衛反応です。
興味深いのは、この攻撃性が出産後の限られた期間だけ現れること。授乳が終わると、母親は再び穏やかな性格に戻ります。つまり、この行動は“本能的”ではありながら、“一時的にスイッチが入る”現象なのです。
この「母性攻撃」は、単なる情動の爆発ではありません。
背後には、脳がホルモンの変化を感知し、特定の神経回路を再構成するという、極めて精密なメカニズムが働いています。
では、どのようにして脳が“優しい母”から“戦う母”へと変わるのでしょうか?
次の章では、その鍵を握る脳の領域──「腹側乳頭前核(PMv)」に迫ります。
鍵を握るのは脳のPMv──眠っていた回路が目を覚ます
今回の研究で注目されたのは、脳の奥深くにある「腹側乳頭前核(ventral premammillary nucleus, PMv)」という領域です。
この部分は、以前から“攻撃行動に関わる場所”として知られており、特にオスのマウスでは、縄張り争いや社会的順位を決めるときに活発に働くことがわかっています。
しかし興味深いのは──
メスの脳にも同じ回路が存在するのに、普段はまったく動いていないという点です。
つまり、女性の脳にも“攻撃のための回路”は備わっているけれど、通常は“眠っている”状態にあるということ。
研究チームは、出産前後のメスのマウスを比較し、このPMv内の「PMvDATニューロン」という神経細胞に注目しました。
すると、出産や授乳の時期になると、この細胞が急に興奮しやすい状態(過興奮)に切り替わることが分かったのです。
電気的な活動を詳しく調べると、
- 授乳期の母マウスでは、これらの細胞が頻繁に発火
- 出産前のメスや、攻撃性を示さない母マウスでは、静かな状態のまま。
まさに、「眠れる回路が覚醒する瞬間」が観察されたのです。
そしてこのPMvDATニューロンを人工的に刺激すると、母マウスはすぐに攻撃的な行動をとるようになり、逆にこの細胞の働きを止めると攻撃が消える──。
この結果から、PMvは“母性攻撃のスイッチ”そのものであることが示されました。
では、そのスイッチを押す“指”にあたるのは何なのか?
次の章では、ホルモンという生体信号の役割に迫ります。
ホルモンがスイッチを押す──プロラクチンとオキシトシンの連携
母マウスの脳で「眠っていた攻撃回路(PMvDATニューロン)」が目を覚ます――
その背後には、授乳期に分泌が高まる2つのホルモンが深く関わっていました。
それが、
- プロラクチン(Prolactin):乳汁分泌を促すホルモン
- オキシトシン(Oxytocin):授乳や絆づくりに関係する“愛情ホルモン”
です。
研究チームは、この2つのホルモンがPMvDATニューロンにどんな影響を与えるのかを、電気生理学的に調べました。
すると驚くべきことに──
どちらのホルモンも、この神経を直接“興奮させる”作用を持っていたのです。
🔹 プロラクチンの働き
プロラクチンを脳切片に加えると、PMvDATニューロンが自発的に発火しやすくなり、電気的活動が増加しました。
さらに、ニューロンが発する電気信号の形(活動電位)そのものも変化し、神経伝達物質の放出が強まることが確認されました。
つまり、プロラクチンは神経を「スタンバイ状態」から「戦闘モード」に押し上げるホルモンなのです。
🔹 オキシトシンの働き
次にオキシトシンを作用させると、同じくPMvDATニューロンが脱分極して活性化。
しかも、その効果はオキシトシン受容体だけでなく、バソプレシン受容体という別の受容体も介して起きている可能性が示唆されました。
つまり、オキシトシンもプロラクチンと協力しながら、脳を「守る母親モード」に切り替える信号を出しているわけです。
ただし、これらのホルモンを授乳していないメスの脳に直接注入しても、攻撃行動は起こりませんでした。
これは、「ホルモンだけ」ではなく、出産や授乳を経た脳全体の状態変化が重要であることを示しています。
このように、プロラクチンとオキシトシンは、まるで鍵と鍵穴のように働き、
“母性攻撃”という一時的な行動モードをオンにするスイッチの役割を果たしているのです。
次の章では、このスイッチが押されたとき、脳の中で何が“優先され”、何が“抑えられる”のか──
「母の愛」と「防衛本能」がせめぎ合う瞬間を見ていきましょう。
攻撃と育児は同時にできない?──脳の優先順位のしくみ
母親は、わが子を守るために“戦う”ことができます。
でも同時に、“育てる”ことにも全力を注いでいます。
この2つの行動──攻撃と育児──は、まったく反対の性質を持ちながら、どちらも母性に欠かせない要素です。
では、脳はどうやってこの二つを切り替えているのでしょうか?
研究チームは、母マウスの脳に光刺激を当ててPMvDATニューロンを人工的に活性化し、その行動を観察しました。
すると驚くべき結果が。
攻撃対象の“侵入者”がいない状況でも、PMvDATニューロンを刺激しただけで、母マウスは仔を世話する行動をやめてしまったのです。
普段ならすぐに子どもを巣へ戻す「仔の回収(pup retrieval)」行動が、まるで止まったかのように。
つまり、この神経回路が動くと、脳は「いまは育児よりも防衛を優先せよ」と判断するわけです。
母マウスの脳では、育児と攻撃という2つの行動プログラムが、同時には動かないよう設計されているのです。
この仕組みは、私たち人間の行動にもどこか通じるものがあります。
危険を察知したとき、私たちは誰かを守るために反射的に行動することがありますが、それは“怒り”ではなく、“防衛のための集中”なのかもしれません。
こうして、脳は状況に応じて優先順位を切り替える。
まるでスイッチをカチッと入れ替えるように──。
次の章では、この研究が示した「性差」や「母性」の新しい見方を紹介します。
「脳の違い」ではなく「スイッチの違い」という、少し驚くような視点です。
科学としてのおもしろさ──性差は“脳の配線”ではなく“スイッチ”だった
これまで、「オスは攻撃的で、メスは穏やか」といった行動の違いは、脳の構造そのものの違い(性的二型性)**によるものだと考えられてきました。
しかし今回の研究は、その常識を覆すような結果を示しています。
つまり──
攻撃行動の回路は、オスにもメスにも“共通して存在している”。
違いは、「いつ」「どんな条件で」その回路が動くか、という“スイッチの入り方”にあったのです。
メスのマウスでは、ふだんこの攻撃回路(PMvDATニューロン)は“眠っている”。
けれど出産・授乳という特別な時期に、ホルモンの変化がその眠れる回路を一時的に“オン”にする。
まるで、潜在していたプログラムが呼び起こされるように、脳が防衛モードに切り替わるのです。
この仕組みは、「脳は固定的ではなく、柔軟に再構成される」という近年の神経科学の考え方とも一致します。
つまり、性差とは“脳のハードウェアの違い”ではなく、“ソフトウェアの設定変更”のようなもの。
状況やホルモン環境によって、同じ回路がまったく異なる行動を生み出す──それが脳の驚くべき可塑性です。
この視点に立てば、「母性攻撃」は単なる情動の爆発ではなく、進化によって備わった柔軟な行動戦略だといえるでしょう。
普段は封印されているけれど、必要なときにだけ発動する。
まさに“眠れる戦士”のような神経回路なのです。
ヒトへの示唆──母性の強さは生物としての適応戦略
マウスの研究とはいえ、この発見は私たち人間の「母性」にも深い示唆を与えてくれます。
母親が“強くなる”のは、気合いや性格の問題ではなく、脳とホルモンがつくり出す自然な生理現象なのです。
授乳期の女性では、プロラクチンやオキシトシンの分泌が増え、子どもへの愛情や絆を強めると同時に、危険を察知する感受性も高まります。
これは「過保護」でも「イライラ」でもなく、生存のための防衛モード。
脳が、“いま守るべきはこの子だ”と判断して、優先順位を変えているのです。
この仕組みを理解すると、「母親の情緒の揺れ」や「出産後の敏感さ」を、
“問題”ではなく“適応”として見直すことができます。
脳は、限られた期間だけ「攻撃」と「防衛」を優先するモードに入っているだけ。
それが、母と子の命を守るために進化してきた、生物としての知恵なのです。
そして何より重要なのは、この「攻撃モード」は永続的ではないということ。
授乳期が終われば、脳は再び“穏やかで世話好きなモード”へと戻ります。
まるでスイッチを切り替えるように、脳はその時々に最も必要な行動を選んでいるのです。
“母は強し”とは、愛情と防衛を自在に切り替える脳の力のこと。
それは、人間の母親だけでなく、すべての命をつなぐ「生きるための知恵」でもあります。
まとめ|眠っていた回路が目覚める瞬間
授乳期の母親が見せる“強さ”──それは脳の中で、普段は静かに眠っている神経回路が、ホルモンの合図で一時的に目を覚ます瞬間でした。
脳のPMv(腹側乳頭前核)という領域では、
攻撃に関わる神経細胞がホルモンによって活性化し、「守るために戦う」という母性特有の行動を引き出します。
けれど同時に、育児や授乳といった“穏やかな行動”は一時的に抑えられる。
脳は限られたリソースをどこに使うかを、瞬時に判断しているのです。
このしくみは、私たち人間にも通じるものがあります。
母親だけでなく、誰もが「いま守りたいもののために強くなる」瞬間を持っている。
それは理性ではなく、脳が選んだ生き方なのかもしれません。
「母は強し」──その言葉の裏には、
眠れる回路を呼び覚ます、脳の美しいプログラムが隠されていました。

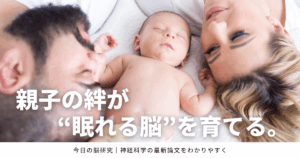
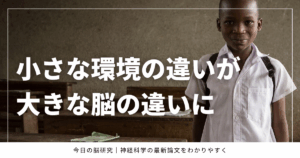
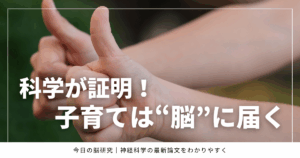

コメント