こんにちは、Dayです!
このブログでは、最新の脳科学論文を一般の方にも楽しめるようにわかりやすくまとめています。
今回のテーマは「母子の絆と赤ちゃんの寝つきの関係」についてです。
フィンランドで行われた大規模な追跡研究によると、母親の“愛着の深さ”が赤ちゃんの睡眠に大きく関わっていることがわかりました。母親の気持ちがうまく赤ちゃんに伝わらないと、夜に何度も起きたり、なかなか寝つけなかったりすることがあるそうです。
また一方で、父親の愛着との関係はやや異なる結果になりました。
この記事では、母親・父親それぞれの「心のつながり」と睡眠の科学的な関係をわかりやすく紹介します。
本記事は、以下の研究をもとにしました。
Rusanen, E., Flykt, M., Kylliäinen, A., Saarenpää-Heikkilä, O., & Paavonen, E. J. (2025). Are maternal and paternal bonding problems associated with child sleep problems at 8 and 24 months? Infant Behavior and Development, 80, 102123.
https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2025.102123
赤ちゃんが「寝ない」のはなぜ?
生後8か月から2歳前後にかけて、「なかなか寝ない」「夜中に何度も起きる」と悩む家庭はとても多いものです。
実は、これは発達の自然なプロセスでもあります。赤ちゃんの脳や体のリズムがまだ大人のように整っていないため、睡眠の質や長さが不安定になりやすいのです。
赤ちゃんの眠りを左右するのは、生理的な要因だけではありません。
たとえば、夜中に目を覚ましたときに「そばに誰かがいる」と感じられると安心して再び眠れますが、逆に環境が変わったり、不安を感じたりすると再入眠が難しくなります。
つまり、赤ちゃんにとって眠りとは「安心して一人になれる力」でもあるのです。
研究でも、生後8〜24か月ごろの赤ちゃんは「親から離れる不安(分離不安)」が強くなる時期とされています。
特に夜は、暗さや静けさが不安を増幅させやすく、「親との心理的なつながり」=愛着の深さが眠りの安定に関係すると考えられています。
このように、「寝ない」という行動の裏には、ただの生活リズムの乱れではなく、親子の関係性や安心感の発達が関わっていることが、近年の研究から少しずつ明らかになってきています。
「母子の絆」と睡眠の意外な関係
今回紹介するフィンランドの研究では、母親の愛着の深さ(bonding)と赤ちゃんの睡眠の関係が詳しく調べられました。
対象は1,000組を超える親子。子どもが生後8か月と2歳(24か月)のときに、親の「愛着の状態」と赤ちゃんの「睡眠の様子」を追跡したのです。
結果はとても興味深いものでした。
母親の愛着がうまく形成されていない場合、赤ちゃんは寝つきにくく、夜中に何度も目を覚ます傾向が見られたのです。
しかもその影響は一時的なものではなく、2歳になっても続いていたことがわかりました。
心理学的に言えば、赤ちゃんにとって眠りとは「親との分離体験」でもあります。
寝る=ひとりになる、ということ。
母親との関係が安心感に満ちていれば、赤ちゃんはその“離れる瞬間”を怖がらずにすみます。
逆に、母親の心に不安や距離感があると、赤ちゃんは眠りを通してその不安を敏感に感じ取ってしまうのです。
さらに、母親のうつ傾向(気分の落ち込み)が強い場合には、愛着形成がうまくいかず、それが間接的に子どもの睡眠の乱れにつながることも示されました。
つまり、「母親のメンタル → 愛着 → 子どもの睡眠」という“こころの連鎖”が存在するのです。
父親の愛着はどう関わる?
母親との関係が赤ちゃんの睡眠に影響していた一方で、父親の愛着の深さは睡眠問題とは明確な関連が見られませんでした。
この結果を見て、「じゃあお父さんは関係ないの?」と思う人もいるかもしれませんが、そうではありません。
研究チームは、当時の社会的背景に注目しています。
フィンランドでは育児休暇制度が整っていますが、調査期間(2011〜2013年)は、実際には母親が約9割以上の育休を取得していました。
そのため、日常的に赤ちゃんと過ごす時間が長いのは母親で、寝かしつけや夜間の対応も母親が担うことが多かったのです。
この“日常的な関わりの濃さ”が、睡眠との関係に差を生んだ可能性があります。
一方で、父親のうつ傾向は、24か月(2歳)の時点で子どもの睡眠と弱く関係していました。
これは、子どもが成長して母親の育休が終わるころ、父親の育児参加が増える時期と重なっているためと考えられます。
つまり、父親の心の状態も、子どもが安心して眠るための“静かな土台”になっているのです。
また、過去の研究では、父親が夜間のケアや寝かしつけに積極的に関わると、赤ちゃんの夜泣きが減り、母親のストレスも軽くなることが報告されています。
今回の研究ではその影響が数値としては明確に出なかったものの、父親の存在が家庭全体の“睡眠リズム”を安定させる重要な役割を果たしていることは間違いありません。
授乳と睡眠の関係も明らかに
今回の研究では、母乳育児と赤ちゃんの睡眠についても分析が行われました。
結果は少し意外かもしれませんが、母乳で育てられている赤ちゃんは、ミルク育児の子よりも夜中に目を覚ましやすい傾向があったのです。
ただし、これは「悪いこと」ではありません。
母乳育児の赤ちゃんは、授乳のタイミングで自然に目を覚ますことが多く、母親との“夜間の触れ合い”を通して安心感を得ているとも考えられます。
つまり、頻繁に起きること自体が、母子のリズムを作る一部になっているのです。
研究チームは、母乳育児と睡眠の関係は「愛着の問題によるものではない」とも報告しています。
授乳の有無によって母子の絆が弱まるわけではなく、授乳と愛着はそれぞれ別の仕組みで子どもの睡眠に影響するようです。
また、母乳で育てている親は夜間の世話が多いため、赤ちゃんの覚醒に気づきやすく、結果として“寝ないように感じる”という側面もあります。
つまり、実際の睡眠リズム以上に、「親の体験」としての睡眠不足が強く残ることがあるのです。
このことから、夜中に起きることを単なる「問題」と捉えるよりも、
「子どもが安心を確かめている時間」
として受け止める視点も大切だと、研究は示唆しています。
科学が教える「よく眠る親子関係」のヒント
この研究が伝えているのは、「赤ちゃんの睡眠」は単なる生活習慣の問題ではなく、親子の“心のリズム”が深く関わっているということです。
つまり、「どう寝かせるか」だけでなく、「どんな気持ちで関わるか」が眠りの安定に影響します。
🕯 ① 寝かしつけの“安心のパターン”をつくる
赤ちゃんは予測できる世界に安心します。
毎晩ほぼ同じ時間に、同じ順序で(お風呂 → 授乳 → 絵本 → 就寝など)過ごすことで、「そろそろ眠る時間だ」と脳が覚えるのです。
こうした習慣の積み重ねが、愛着にも良い影響を与えることが知られています。
💞 ② 親自身のメンタルケアを大切に
母親の気分の落ち込みやストレスは、赤ちゃんの睡眠リズムにも影響することが今回の研究で示されました。
もし「寝かしつけがつらい」「イライラしてしまう」と感じたら、それはサインです。
家族や専門家に少し頼ることが、赤ちゃんの眠りを守る第一歩になります。
「親の安心が、子どもの安心をつくる」――これは神経科学的にも確かな関係です。
🧸 ③ 父親も“夜の時間”に関わる
夜の寝かしつけや夜泣き対応を、父親が少しでも分担することで、母親の疲労が減るだけでなく、赤ちゃんが“両親のリズム”に安心を覚えるようになります。
短時間でも構いません。抱っこで寝かしつけたり、寝室に顔を出したりするだけでも、赤ちゃんは“家族に守られている”と感じやすくなるのです。
🌙 ④ 完璧を目指さない
赤ちゃんの睡眠は個人差が大きく、研究で示された傾向も「平均的な傾き」にすぎません。
眠れない夜があっても、それは一時的なもの。
大切なのは、眠れない時間を“つらい夜”ではなく、“寄り添う夜”に変えていくこと。
このように、科学が示す「よく眠る親子関係」とは、規則正しいスケジュールよりも、“安心と一貫性”を感じられる関係性そのものなのです。
まとめ|母子の絆を育てることは、眠りを育てること
赤ちゃんの「眠り」は、ただの生理現象ではなく、心の発達を映す鏡でもあります。
今回紹介した研究では、母親の愛着の深さが赤ちゃんの睡眠と強く関わること、そして母親の気分の落ち込み(産後うつ)がその愛着を通して影響することが示されました。
一方で、父親の愛着も、家族全体の安心を支える見えない土台になっています。
直接的な影響が数字に表れなくても、「お父さんがそばにいる」ことが、母子の安定に大きく貢献しているのです。
夜に何度も泣いて起きる赤ちゃんを前に、途方に暮れることもあるでしょう。
でも、そのたびに抱きしめ、声をかけ、安心を伝えてきた時間は、確実に親子の絆を深めています。
赤ちゃんが少しずつ一人で眠れるようになるのは、「安心して離れられる」ほど信頼が育った証。つまり、よく眠るようになること=心の成長のサインなのです。
焦らず、比べず、寄り添いながら。
眠りを通して育つ「親子の信頼関係」を、今日も大切にしていきましょう。

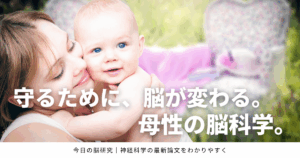
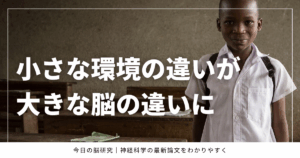
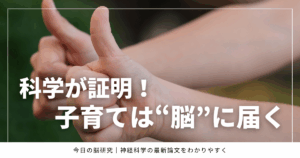

コメント