こんにちは、Dayです!
このブログでは、最新の脳科学論文を一般の方にも楽しめるようにわかりやすくまとめています。
今回のテーマは「まだ診断されない“隠れうつ”を表情から読み取る最新研究」についてです。
うつ病と診断されるほどではないけれど、気分の落ち込みや無気力さを抱える「サブしきい値うつ」。この状態は将来のうつ病リスクを高めることが知られていますが、本人も周囲も気づかないことが多いのが現実です。
最新の研究では、この“隠れうつ”のサインが顔の表情や他者からの印象に現れていることが明らかになりました。この記事では、その科学的な発見と、日常生活にどうつながるのかをわかりやすく解説していきます。
本記事は、以下の研究をもとにしました。
Sugimori, E., & Yamaguchi, M. (2025). Subthreshold depression is associated with altered facial expression and impression formation via subjective ratings and action unit analysis. Scientific Reports, 15, Article 30761.
https://doi.org/10.1038/s41598-025-15874-0
サブしきい値うつとは? ― 診断されない“隠れうつ”
「うつ病」と聞くと、多くの人は日常生活に支障をきたすほどの強い気分の落ち込みや無気力をイメージするでしょう。しかし、その手前の段階として存在するのが「サブしきい値うつ」です。
これは、臨床的なうつ病と診断されるほど重くはないものの、気分が落ち込みやすかったり、やる気が出にくかったりと、軽度の抑うつ症状を抱えている状態を指します。
サブしきい値うつは「隠れうつ」とも呼ばれることがあり、本人や周囲が気づかないまま過ごしてしまうケースも少なくありません。しかし研究によって、この状態の人は将来的に本格的なうつ病へと移行するリスクが高いことがわかっています。
つまり、「まだ病気ではないから大丈夫」と放置してしまうのではなく、「心の健康のイエローカード」として理解しておくことが大切なのです。
表情と印象の研究方法 ― 大学生を対象にした実験
今回紹介する研究では、日本の大学生を対象に「顔の表情」と「他人からの印象」を分析しました。研究の流れは大きく分けて2つあります。
まず、参加者は 自己紹介の短いビデオ(約10秒) を撮影しました。その映像を別の大学生たちに見てもらい、「表情が豊かかどうか」「自然に見えるか」「親しみやすさがあるか」など、いくつかの項目で印象を評価してもらいました。これによって、「サブしきい値うつ(隠れうつ)の人」と「そうでない人」とで、他者からの印象にどんな違いがあるのかを調べたのです。
次に、ビデオ映像を コンピュータ解析ソフト(OpenFace 2.0) にかけ、顔の細かい動きを数値化しました。このソフトは「アクションユニット(AU)」と呼ばれる顔の筋肉の動きを自動的に抽出できます。たとえば「眉を上げる」「まぶたを開く」「口を横に引く」といった動作を、1フレームごとに検出することができるのです。
このようにして、主観的な評価(人がどう感じるか) と 客観的なデータ(顔の筋肉の動き) の両面から「隠れうつ」の特徴を明らかにしようとしました。
見えてきた結果 ― 隠れうつの人はどう見える?
研究の結果、サブしきい値うつ(隠れうつ)の人は、健常な人と比べて 「ポジティブな印象が弱く評価される」 ことがわかりました。
具体的には、ビデオを見た他の学生たちは、隠れうつの人に対して
- 「表情があまり豊かではない」
- 「自然さが少ない」
- 「親しみやすさや好感度が低い」
といった印象を持ちやすい傾向がありました。
ここで注目すべきは、ネガティブな印象(暗い、不安そう、偽っているなど)が強まったわけではなかったという点です。むしろ、「明るさや親しみやすさが減って見える」という、ポジティブさの欠如が特徴的でした。
さらに、顔の筋肉の動きを分析すると、隠れうつの人では 眉やまぶた、口の周りの微細な動きに違いが見られました。これらの変化は人間の目では気づきにくい小さなものですが、コンピュータ解析でははっきりと差が検出されていました。
つまり、本人や周囲が「大きな変化はない」と思っていても、表情の中には確かに“心のサイン”が隠れているのです。
なぜ科学的に面白いのか?
この研究が興味深いのは、「まだ病気と診断される前の段階」であっても、心の状態が顔の表情に反映されていることを示した点です。
私たちは普段、誰かの顔を見て「元気そうだな」「なんとなく疲れてそう」と感じ取ります。しかし、そうした印象の背後には、実際に眉や口元のわずかな筋肉の動きが関係していることが、この研究で裏付けられました。
さらに注目すべきは、主観的な評価(他人の印象) と 客観的なデータ(顔の筋肉の動き) を両方組み合わせたことです。人間の直感だけでなく、AIを用いた細かい数値解析によって「隠れうつ」の特徴が一貫して確認されたのです。
また、この研究は日本の大学生を対象に行われました。表情の豊かさや表現の仕方は文化によって異なります。欧米の研究では「笑顔の多さ」が重視されることが多いですが、日本ではもともと控えめな表現が一般的です。そうした文化的背景を踏まえても、「隠れうつ」ではさらに表情が乏しく見えるという結果は、国際的にも意義があります。
つまり、この研究は「顔」という誰にでも見えるサインを通じて、心の健康を理解しようとする新しい一歩であり、うつ病の予防や早期発見に役立つ可能性を秘めているのです。
日常生活へのヒント ― 早めに気づくために
今回の研究は、「隠れうつ」のサインが日常的な表情に表れていることを示しました。これは専門家だけでなく、私たちの生活にも役立つヒントを与えてくれます。
まず大切なのは、「ネガティブな表情が増える」のではなく「ポジティブな表情が減る」という点です。たとえば、笑顔が少なくなったり、会話中に自然な表情が出にくくなったりすることは、心の疲れを示すサインかもしれません。
また、周囲の人がその変化に気づくことも重要です。「最近なんだか元気がなさそうだな」「笑うことが減ったな」と感じたとき、軽く声をかけたり、一緒に過ごす時間を持ったりすることで、本人が安心できるきっかけになることがあります。
さらに、職場や学校の場面でもこの知識は役立ちます。表情の変化は一見小さなものですが、早めに気づけば本格的なうつ病に進行する前にサポートを始められる可能性があります。
もちろん、表情だけでうつを判断することはできません。しかし、「顔に出る小さなサイン」を意識することで、自分自身や大切な人の心の健康に気づく手がかりになるのです。
まとめ ― 表情に潜む“心のサイン”を理解する
今回ご紹介した研究では、「サブしきい値うつ(隠れうつ)」と呼ばれる軽度の抑うつ状態が、顔の表情や他人からの印象に微妙な変化をもたらすことが明らかになりました。
特に重要なのは、ネガティブな表情が増えるのではなく、ポジティブな表情が減ってしまう という点です。こうした特徴は、本人や周囲が見過ごしやすいため、「気づかれないまま進行してしまう」リスクがあります。
この研究は、AIによる表情解析と人による主観評価を組み合わせた点でも新しく、将来的には うつ病の早期発見や予防的ケア に役立つ可能性があります。
もちろん、表情だけですべてを判断することはできません。しかし、日常の中で「ちょっと笑顔が減ったな」と感じたとき、それを心のサインとして受け止める視点を持つことは、自分や大切な人を守る第一歩になるでしょう。


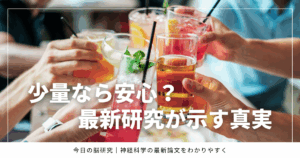
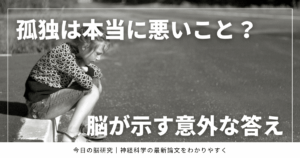
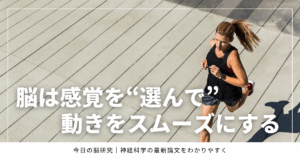

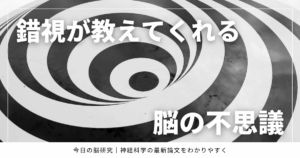
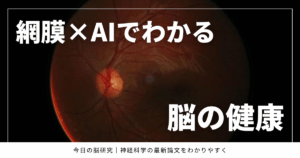
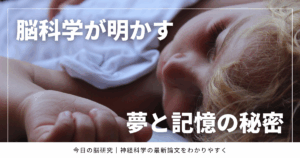
コメント